どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
行政書士試験の法令科目は「法学基礎」「憲法」「行政法」「民法」「商法」の計5科目あります。このうち、1番配点が高いのが行政法です。
行政法から出題数も多く、試験範囲は広いです。そのため、効率の良い行政法の学習方法が分からず、全範囲の学習ができずに困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
私は、2020年の行政書士試験に独学で一発合格することができました。
そんな私が、本記事にて、行政法の過去問の出題傾向、出題傾向を踏まえた対策方法を解説します。これから行政法の学習を始める方の参考になりますと幸いです。
出題数・配点割合
法令科目の点数内訳と配点割合をまとめたものが以下の表になります。
| 科目 | 5肢選択式 | 配点 | 多肢選択式 | 配点 | 記述式 | 配点 | 合計 | 配点割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎法学 | 2問 | 8点 | 8点 | 3% | ||||
| 憲法 | 5問 | 20点 | 1問 | 8点 | 28点 | 11% | ||
| 行政法 | 19問 | 76点 | 2問 | 16点 | 1問 | 20点 | 112点 | 46% |
| 民法 | 9問 | 36点 | 2問 | 40点 | 76点 | 31% | ||
| 商法 | 5問 | 20点 | 20点 | 8% | ||||
| 合計 | 40問 | 160点 | 3問 | 24点 | 3問 | 60点 | 244点 | 100% |
行政書士試験は全部で60問出題されますが、このうち行政法は計22問(5肢選択式が19問、多肢選択式が2問、記述式が1問)出題されます。
法令科目の合計は244点ですが、そのうちの112点(割合換算すると46%)を行政法が占めています。
過去5年分の出題範囲
過去5年分の行政法の5肢選択式(計19問)の試験分野別の出題数をまとめました。
| 出題数 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法理論 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 行政手続法 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 行政不服審査法 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 行政事件訴訟法 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 国家賠償法 (・損失補償) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 地方自治法 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 複合問題 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 合計 | 19問 | 19問 | 19問 | 19問 | 19問 |
行政法の試験範囲は、「一般的な法理論(義務の履行確保の手段など)」「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」「国家賠償法・損失補償」「地方自治法」「複合問題」の7つの分野に大分できますが、毎年、各分野からの出題数は決まっているのが特徴です。
また、過去5年間の多肢選択式・記述式(計3問)の出題範囲をまとめました。
| NO. | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第44問(多肢選択式) | 行政事件訴訟法 | 行政手続法 | 行政指導 (行政手続法) | 義務の履行 確保の手段 (一般的な法理論) | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 ・行政不服審査法 |
| 第45問(多肢選択式) | 一般的な法理論 | 行政事件訴訟法 | 国家賠償法 | 行政手続法 | 国家賠償法 |
| 第46問(記述式) | 行政事件訴訟法 | 行政手続法 | 抗告訴訟 (行政事件訴訟法) | 行政手続法 行政事件訴訟法 | 抗告訴訟 (行政事件訴訟法) |
多肢選択式と記述式に関しては、行政手続法や行政事件訴訟法からの出題が多いです。
※厳密に言えば、行政法の範囲はとても広い。
誤解されがちですが、「行政法」という法律は存在しません。
全法律の8~9割が、行政法に該当するとも言われています。当然ながら、これら全ての範囲から出題されるわけではありません。
出題形式は、各試験により様々です。例えば、司法試験では、初見の法律が出題され、その法律の規定に「裁量があるか?」「処分に該当するか?」といった内容が出題されます。
ただ、行政書士試験の行政法では、「行政法の一般的な法理論」・「行政手続法」・「行政不服審査法」・「行政事件訴訟法」・「国家賠償」・「地方自治法」が出題の中心とされています。いきなり初見の法律が出題されることは少ないです。
なので、テキストや参考書に記載の範囲を学習するようにしましょう。
得点目標(5肢選択式):15/19問は正解したい。
問題の難易度や配点割合を考慮すると、行政法の5肢選択式は15/19問(約80%)は正解したいところです。
満点を狙うべき分野:行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法(11問)
5肢選択式の中でも、行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法は、満点を目指しましょう。
この4つの法律の問題は、比較的に難易度が低く、安定して点数が取りやすいです。各法律の条文は、多くて70条程度で、覚える判例もそこまで多くないため、試験範囲も広くありません。
また、この4つの法律は多肢選択式や記述式で出題されることも多く、勉強効率が良いです。
この4つの法律は非常に大事なので、学習上のポイントを別記事にて詳細に解説しております。併せてご覧ください。
50%程度正解すべき分野:総論・地方自治法・複合問題(8問)
その他の科目は、試験範囲が広く対策が難しいので、50%程度正解できればOKです。細かい知識はなくても、重要判例を押さえておけば50%程度は正解することができます。
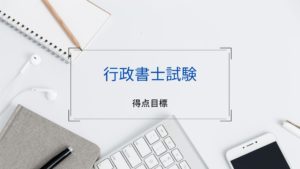
得点目標(多肢選択式):6/8程度(75%)は正解したい。
多肢選択肢は、判例や条文の穴埋めに関する出題が多いです。条文や判例の細かい文言を暗記して、75%程度は得点したいところです。
得点目標(記述式):50%程度は正解したい。
行政法の記述式は1問のみ出題されますが、20点を占めているので、対策は必須です。
記述式は50%程度は獲得したいところです。普段から判例と条文に則した勉強をしたおけば、50%程度得点することは難しくありません。
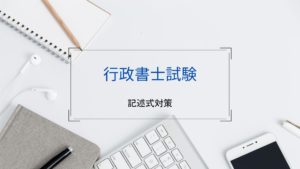
結論:「行政法」の出題内訳を押さえて、それぞれの法律ごとの本番での目標得点を決めましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。
行政法は一番出題範囲が広く、行政法の理解が合否を分けますので、それぞれの法律ごとの目標得点を決めて、合格点を取れるような学習をしていきましょう!
他の法令科目の勉強法も別記事にて解説しておりますので、併せてご覧ください。
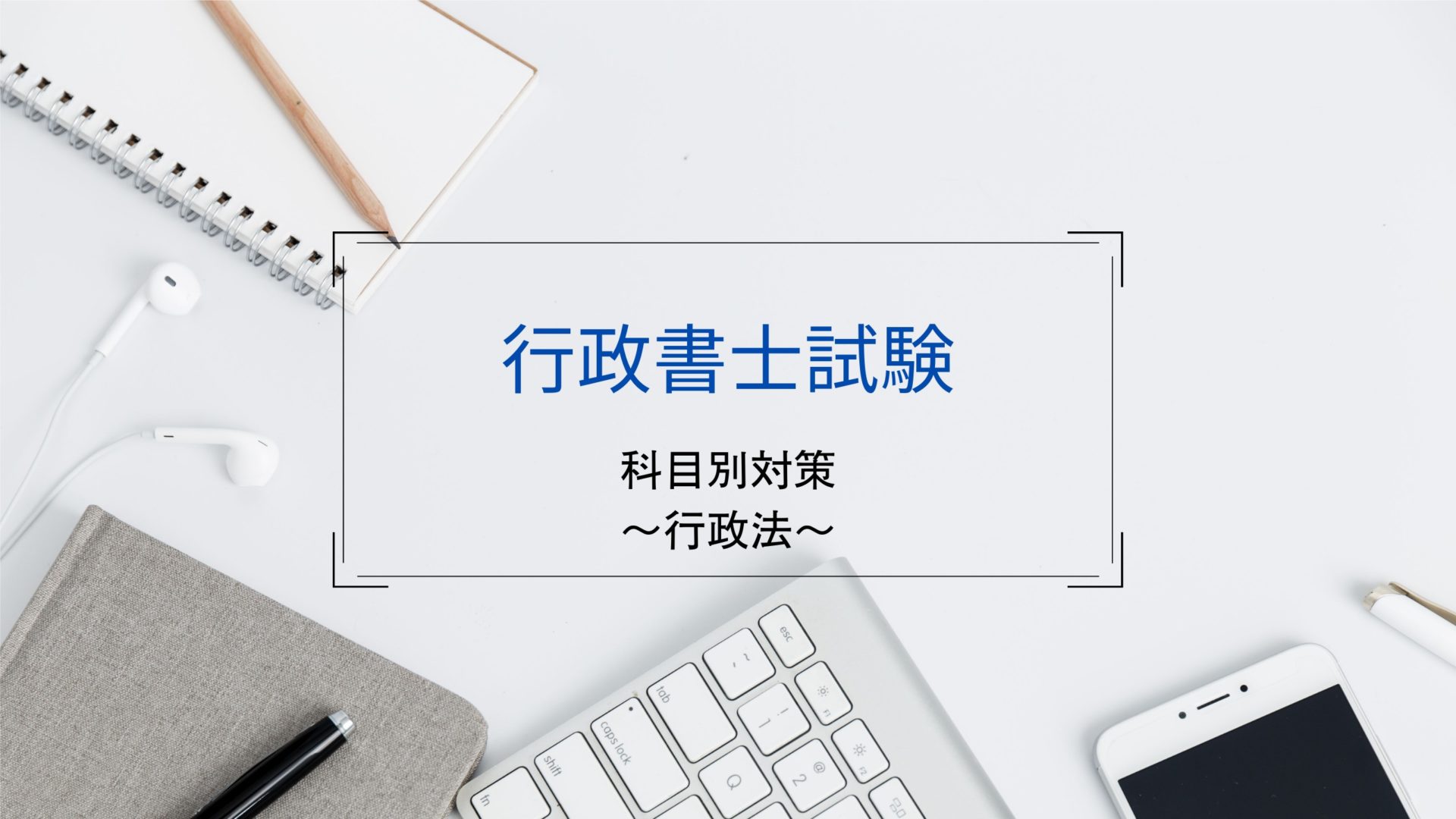
コメント