どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
行政事件訴訟法は、5肢選択式にて毎年3問(12点分)程度出題されます。配点自体は高くないものの、問題の難易度は低いので、出来れば満点を獲得したい分野です。
もっとも、行政事件訴訟法の出題範囲は広く、暗記すべき条文も多いので、苦手な方も多いのではないでしょうか?
私は、2020年度の行政書士試験に独学で一発合格することができました。
そんな私が、本記事で、行政事件訴訟法の条文学習の学習ポイントや、押さえるべき事項について解説します。行政事件訴訟法の学習方法について悩んでいる方の参考になりますと幸いです。
出題範囲:条文と判例のいずれからも出題される。
行政事件訴訟法の問題では、条文知識と判例知識の同じくらいの割合で問われます。
本記事では、行政事件訴訟法の条文の学習ポイントについて解説します。(行政事件訴訟法は範囲が広いため、2記事に分けて解説します。)
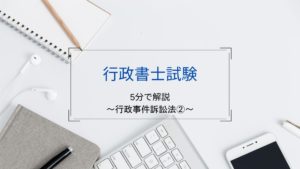
ポイント①:行政訴訟の種類・訴訟要件を整理しましょう。
行政訴訟法に規定されている訴訟の種類、訴訟の内容・訴訟要件や手続を整理したものが、以下の表になります。
| 行政事件訴訟の種類(2条) | 各訴訟の内容 | 訴訟要件・手続等 | |
|---|---|---|---|
| 主観訴訟 | 抗告訴訟(3条1項) | 処分取消訴訟(3条2項) | 9条~35条 |
| 裁決取消訴訟(3項3項) | 9条~35条 | ||
| 無効等確認訴訟(3条4項) | 36条 | ||
| 不作為の違法確認訴訟(3条5項) | 37条 | ||
| 非申請型義務付訴訟(3条6項1号) 申請型義務付訴訟(3条6項2号) | 37条の2 37条の3 | ||
| 差止訴訟(3条7項) | 37条の4 | ||
| 当事者訴訟(4条) | 形式的当事者訴訟(4条前段) | 39条~41条 | |
| 実質的当事者訴訟(4条後段) | 40条~41条 | ||
| 客観訴訟 | 民衆訴訟(5条) | 42,43条 | |
| 機関訴訟(6条) | 42,43条 |
行政事件訴訟法の条文は全部で46ありますが、まずは行政事件訴訟法の全体の条文構造が理解するためにも、この表は頭に入れておきましょう。
行政事件の4つの種類(第2条)
第2条によると、行政事件訴訟の種類として、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の4つが規定されています。
なお、抗告訴訟と当事者訴訟は「主観訴訟」、民衆訴訟と機関訴訟はそれぞれ「客観訴訟」に区分されます。
主観訴訟は、個人の権利利益の救済を目的とし、自分自身に直接関係する行政活動に対する訴訟を指し、客観訴訟は、行政の適法性の確保を目的とし、自分には直接関係ない行政活動に対する訴訟を指します。
「抗告訴訟」と「当事者訴訟」の各種類(第3条各項、第4条各項)
第3条と第4条に、抗告訴訟と当事者訴訟の具体的な訴訟(少区分)が規定されています。
特に大事なのは、抗告訴訟中の具体的な訴訟名(処分取消訴訟・非申請型義務付訴訟など)です。種類が沢山ありますが、可能であれば全て覚えてましょう。
各訴訟の訴訟要件(第9条など)
各訴訟の訴訟要件(原告適格など)が、9条以下に規定されております。まずは取消訴訟の訴訟要件を規定して、その他の訴訟に関して取消訴訟の訴訟要件や手続が被る部分は、条文を適宜準用する、という条文構造になってます。
この条文構造を理解したうえで、各訴訟の種類・訴訟要件を理解しましょう。
ポイント②:まずは取消訴訟の訴訟要件・その他手続を理解しましょう。
行政事件訴訟法の中で基本的(スタンダード)な訴訟類型が、「取消訴訟」ですので、まずは取消訴訟の訴訟要件その他の手続を理解しておきましょう。
訴訟要件
取消訴訟の中で、訴訟要件として挙げられているものは、以下の5つです。
- 処分性(3条1項)
- 原告適格・訴えの利益(9,10条)
- 被告適格(11条)
- 管轄(12(,13)条)
- 出訴期間(14条)
5つのうちで重要度が高いものは、処分性と原告適格と出訴期間です。このうち「処分性」と「原告適格」は判例からの出題が多いため、条文知識としては「出訴期間」が重要になります。
(出訴期間)第十四条
取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
e-Gov法令検索
2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
第14条は暗記しておきましょう。重要な箇所は赤線・マークを付しましたので、違いにも着目しつつ覚えるようにしましょう。
訴訟手続・執行停止・判決の効力など
訴訟要件以外の、取消訴訟の手続きや効力など(移送・執行停止・請求の併合・判決の効力)を理解してください。
- 訴訟形態(16条~23条)
- 執行停止(25条~29条)
- 判決の取消・その効力(30条~35条)
行政事件訴訟法は条文が少なく、3ついずれも試験で出題されるので全て重要ですが、あえて重要度を付けると、「執行停止」→「判決の取消・その効力」→「訴訟形態」です。
(執行停止)第二十五条
処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2 処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。
3 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
4 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
5 第二項の決定は、疎明に基づいてする。
6 第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
7 第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
8 第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。
執行停止の中でも、特に大事なのが第25条です。重要事項については暗記しましょう。
ポイント③:その他抗告訴訟の訴訟要件・準用条文を理解しましょう。
その他の抗告訴訟の訴訟要件は、第36条以降に記載されています。
上記の取消訴訟の条文を準用しますので、各訴訟の訴訟要件と準用条文を理解しましょう。
特に、抗告訴訟の準用条文の第38条、当事者訴訟の準用条文の第41条、民事訴訟及び機関訴訟の準用条文の第43条は大事なので、引用しておきます。
(取消訴訟に関する規定の準用)第三十八条
第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
3 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
4 第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。
(抗告訴訟に関する規定の準用)第四十一条
第二十三条、第二十四条、第三十三条第一項及び第三十五条の規定は当事者訴訟について、第二十三条の二の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。
2 第十三条の規定は、当事者訴訟とその目的たる請求と関連請求の関係にある請求に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合における移送に、第十六条から第十九条までの規定は、これらの訴えの併合について準用する。
(抗告訴訟又は当事者訴訟に関する規定の準用)第四十三条
民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、第九条及び第十条第一項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。
2 民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の無効の確認を求めるものについては、第三十六条の規定を除き、無効等確認の訴えに関する規定を準用する。
3 民衆訴訟又は機関訴訟で、前二項に規定する訴訟以外のものについては、第三十九条及び第四十条第一項の規定を除き、当事者訴訟に関する規定を準用する。
各条文が準用している訴訟・準用条文について、具体的に把握しておきましょう。
以下、取消訴訟以外の訴訟の訴訟要件と準用条文をまとめたものです。
- 無効確認訴訟:第36条にて訴訟要件(原告適格)を規定。その他要件は38条1項,2項,3項にて準用。
- 非申請型義務付け訴訟:第37条の2にて訴訟要件(原告適格)を規定。その他要件は第38条1項にて準用。
- 申請型義務付け訴訟:第37条の3にて訴訟要件(原告適格)を規定。その他要件は第38条1項にて準用。
- 不作為の違法確認訴訟:第37条にて訴訟要件(原告適格)を規定。その他要件は第38条1項,38条4項にて準用。
- 非申請型義務付け訴訟:第37条の2にて訴訟要件(原告適格)を規定。その他要件は第38条1項にて準用。
- 申請型義務付け訴訟:37条の3にて訴訟要件(原告適格)を規定。その他要件は第38条1項にて準用。
- 差止め訴訟:第37条の4にて訴訟要件(原告適格)を規定。その他要件は第38条1項にて準用。
- (仮の義務付け及び仮の差し止め※いわば執行停止の特則のようなもの):第37条の5 1項~3項にて要件を規定。その他要件は第37条の5 4項にて準用。(主に執行停止の条文の準用)
- 当事者訴訟:第39条,40条にて手続を規定。その他手続は第41条にて準用。
- 民衆訴訟及び機関訴訟:第42条にて訴訟要件(原告適格)を規定。その他要件は第43条にて準用。(※取消訴訟、無効訴訟、当事者訴訟の3種類に分類して準用)
行政事件訴訟法の1番難しいポイントです。条文構造が複雑なため、各訴訟の訴訟要件や準用条文を理解が難しいです。六法などを用いて条文を行ったり来たりしながら、どの訴訟では訴訟要件になるのか自分の中で整理できるようにはなっておきましょう。
まとめ:まずは全体の条文構造の理解から、訴訟要件まで暗記しましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。
行政事件訴訟法は、とにかく各訴訟の訴訟要件・手続等を押さえることが大事です。訴訟要件・手続きを押さえるためには、全体構造や準用条文の理解が必要となりますので、根気強く条文学習を行いましょう。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければ、他の行政法の「5分で解説シリーズ」もご覧ください。
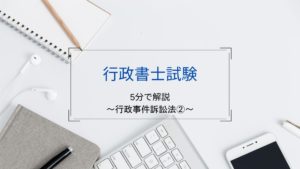
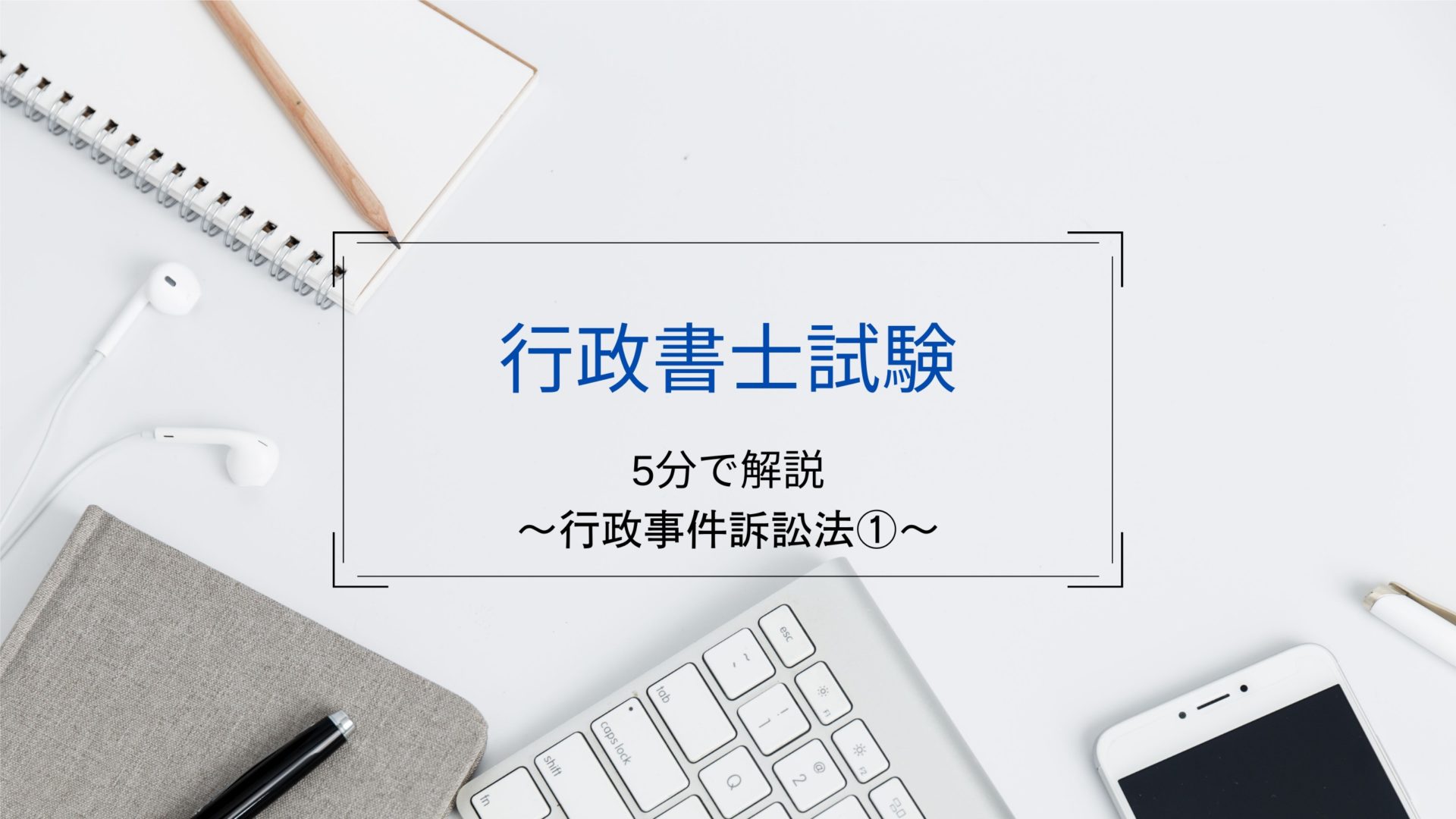
コメント