どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
行政事件訴訟法は、5肢選択式にて毎年3問(12点分)程度出題されます。配点は高くないですが、問題の難易度は低いため、出来れば満点を獲得したい分野です。
もっとも、行政事件訴訟法の出題範囲は広く、押さえるべき判例も多いので、苦手としている方も多いのではないでしょうか?
私は、2020年度の行政書士試験に独学で一発合格することができました。
そんな私が、本記事で、行政事件訴訟法の判例学習の学習ポイントや、押さえるべき事項について解説します。行政事件訴訟法の学習方法について悩んでいる方の参考になりますと幸いです。
出題範囲:条文と判例のいずれからも出題される。
行政事件訴訟法の問題では、条文知識と判例知識の同じくらいの割合で問われます。
本記事では、行政事件訴訟法の判例学習ポイントについて解説します。(行政事件訴訟法は範囲が広いため、2記事に分けて解説します。)
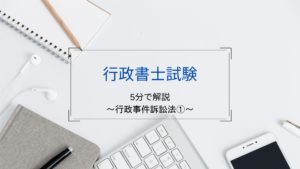
基本的に、「処分性」「原告適格」「訴えの利益」に関する判例が出題される。
行政書士試験の行政事件訴訟法では、基本的に「処分性」・「原告適格」・「訴えの利益」に関する判例が多く出題されるので、この3つの要件に関連する判例は押さえておきましょう。
まず、3つの要件の根拠条文だけは簡単に確認しておきましょう。
処分性(=「処分」)の根拠条文(3条2項)
(抗告訴訟)第三条
2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
3条2項に「処分」という文言があります。処分に該当するか(=処分性が認められるか)について、多くの事案で問題になっている、という点は頭に入れておいてください。
「原告適格」「訴えの利益」の根拠条文(9条)
原告適格と訴えの利益の根拠条文は第9条になります。
(原告適格)第九条
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなつた後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
2 裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。この場合において、当該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たつては、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌するものとし、当該利益の内容及び性質を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。
赤マーク部分の「法律上の利益を有する者」が原告適格、黄色マーク部分の「回復すべき法律上の利益を有する者」が訴えの利益の根拠の文言となります。(※訴えの利益の根拠条文が第9条でないケースもありますので、ご注意ください。)
なお、法律上の利益の有無を判断するにあたっての考慮要素を規定した第9条2項は、超重要条文です。そのまま穴埋め問題として出題される可能性もありますので、可能であれば全て暗記しておきましょう。
ポイント①:「処分性」に関する判例を覚えましょう。
条文を理解した上で、以下、処分性に関して押さえておくべき判例を解説します。
処分性のリーディングケース
まず、処分性を検討するうえで、「処分」の定義が問題となりますが、リーディングケースはS39.10.29の判例です。(ごみ焼却場を設置する行為に、処分性が認められるかどうかが争われた事案です。)
この判例によると、「行政庁の処分」(行政事件訴訟3条2項と同義)とは、「公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められている行為をいう。」と判示しています。
本判例で示した処分性の定義はとても重要なので、正確に暗記しておきましょう。(なお、本判例は結論として、処分性はないと判示しました。)
当該定義ですが、様々な説があるものの、2つの要件に区分して考えるのが一般的です。
- 公権力の主体たる国または公共団体が行う行為であるか。(=公権力性)
- 直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定するかどうか。(=法効果性)
以下、「公権力性」と「法効果性」の要件とで区分して、判例を解説します。
なお、基本的には判例は事件名(事案)と結論だけ覚えればよいです。余裕があれば、併せて理由づけの部分も覚えましょう。
公権力性が争われた判例(2つ)
| 事案 | 処分性 | 理由 |
|---|---|---|
| 労災就学援護費の支給決定(H15.9.4) | ○ | 支給決定によってはじめて具体的な労災就学援護費の支給請求権が発生するため |
| ごみ焼却場設置行為 (S39.10.29) | × | 私法上の契約+内部的手続行為があるに過ぎないため。 |
公権力性に関しては、重要判例は2つしかないので、暗記しやすいです。
法効果性が争われた判例(18つ)
| 事案 | 処分性 | 理由 |
|---|---|---|
| 消防庁の同意 (S34.1.29) | × | 行政機関相互の行為のため |
| 墓地埋葬法の解釈通達 (S43.12.24) | × | 行政機関相互の行為のため |
| 新幹線工事実施計画の認可 (S53.12.8) | × | 行政機関相互の行為のため |
| 輸入禁制品該当の通知 (S54.12.25) | 〇 | 観念の通知だが、法律の規定に準拠し、 かつ貨物を適法に輸入できなくなるという法律上の効果を及ぼすため |
| 公務員の採用内定通知 (S57.5.27) | × | 採用の準備手続としてされる事実上の行為にすぎないため |
| 交通反則金の納付通告 (S57.7.15) | × | 反則金の納付義務を課すものではなく、また、 販促行為に関する争いはもっぱら刑事手続きによることが 道交法上予定されているため |
| 開発許可申請に対する 公共施設管理者の同意 (H7.3.23) | × | 法は同意がある場合に限って開発行為を認めており、 同意を拒否する行為自体は権利ないし法的地位を侵害するものではないこと、 また、同意に関する手続、基準・要件が法定されていないため |
| 食品衛生法違反通知 (H16.4.26) | 〇 | 法律の趣旨に適った行政実務の下で、 輸入許可が受けられないという法的効力を有するため |
| 登録免許税還付通知請求の 拒否通知 (H17.4.14) | 〇 | 簡易迅速に還付を受けることが出来る 手続上の地位を否定する法的効果を有するため |
| 病院開設中止勧告 (H17.7.15) | 〇 | 医療法上は行政指導であるが、勧告不服従により、 相当程度確実に保険利用機関の指定が拒否され、 病院開設を断念せざるを得なくなるため |
| 土地汚染対策法の通知 (H24.2.3) | 〇 | 土地所有者等に調査報告義務を生じさせ、 その法的地位に直接的な影響を及ぼすため |
| 二項道路の一括指定の告示 (H14.1.17) | 〇 | 指定の効果の及ぶ個々の道路は二項道路とされ、 その敷地所有者は具体的な私権制限を受けるため |
| 公立小学校を統廃合する条例 (H14.4.25) | × | 具体的に特定の小学校の教育を受けさせる権利ないし法的地位はないため |
| 水道料金を改定する条例 (H18.7.14) | × | 限られた特定の者らに対してのみ適用されるものではないため |
| 公立保育所を廃止する条例 (H21.11.26) | 〇 | 限られた特定の者らに対して、直接、 当該保育所において保育を受けることを期待し得る法的地位を奪うため |
| 用途地域の指定 (S57.4.22) | × | 法令の制定と同様の、不特定多数者に対する一般的抽象的な制約のため |
| 市町村営土地改良事業施工認可(S61.2.13) | 〇 | 性格を同じくする国営または都道府県営の土地改良事業計画の決定について、 行政上の不服申立ての対象とされているため |
| 土地区画整理事業計画決定 (H20.9.10) | 〇 | 建築規制を伴う事業手続に従って換地処分を受けるべき地位に立たされ、 法的地位に直接的な影響が生じる、および、実効的な権利救済の観点のため |
18個と少し多いですが、頑張って覚えましょう。
全体的に、平成の判例の方が出題されやすい(多肢選択式などでもよく出題されます。)ので、余裕があれば判旨全体を読んでおきたいところです。(もちろん余裕があればでOKです。)
ポイント②:「原告適格」に関する判例を覚えましょう。
リーディングケース
リーディングケースは、主婦連ジュース訴訟判決(S53.3.14)です。
この判決では、行政上の不服申立適格を有する者について、「当該処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害される恐れのある者」とし、「右にいう法律上保護された利益とは、行政法規が私人等権利主体の個人的利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を課していることにより保証されている利益であって、それは、行政法規が他の目的、特に公益の実現を目的として行政権の行使に制約を課している結果たまたま一定のものが受けることとなる反射的利益とは区別されるべきものである」としました。
(※行政不服審査法の不服申立適格に関する訴訟でしたが、取消訴訟の原告適格についても先例とされています。)
本判例のポイントは、以下の2点です。
- 「個人的利益」と「反射的利益」とは区別できる。
- 「法律上保護された利益」と認められるためには、法律が個人的利益を保護していると解されることが必要。
なお、原告適格に関する最高裁の判断枠組みに関しては、丁寧に解説するとかなり長くなるので、省略します。まずは判例や第9条2項の判断枠組みを理解できるようになっておきましょう。
原告適格に関する判例
| 事案 | 原告適格 | 理由 |
|---|---|---|
| 公正競争規約の認定を争う者 (S53.3.14) | × | 景表法の規定により一般消費者が受ける利益は、公益の保護の結果として生ずる反射的な利益ないし事実上の利益に過ぎない。 |
| 公衆浴場の営業許可を争う競業者 (S37.1.19) | 〇 | 適正な許可制度の運用によって保護せらるべき業者の営業上の利益は、公衆浴場法によって保護せられる法的利益と解するを相当とする。 |
| 放送局免許許可を争う競願者 (S43.12.24) | 〇 | 拒否処分と免許付与とは、表裏の関係にあるものである。 |
| 定期航空運送事業免許を争う周辺住民 (S1.2.17) | 〇 | 新規路線免許により生じる航空機騒音によって社会通念上著しい障害を受ける者には、原告適格が認められる。 |
| 原子炉設置許可を争う周辺住民 (H4.9.22) | 〇 | 事故が起こったときは、原子炉施設に近い住民ほど被害を受ける蓋然性が高い。 |
| 総合設計許可に関わる建築物の倒壊・円状により 直接的な被害を受けることが予想される範囲の建物の居住者・所有者 (H14.1.22) | 〇 | |
| 保安林指定解除を争う周辺住民 (S57.9.9) | 〇 | 規定と森林法の沿革とをあわせ考えると、法は「直接の利害関係を有する者」に利益主張できる地位を法律上府としているものと解するのが相当。 |
| 林地開発許可について開発行為によって起こり得る土砂の流出・崩壊、水害等の災害により生命・身体等に直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者・財産権を有する住民 (S13.3.13) | 居住者は〇 財産権者は× | 森林法は開発区域に近接する一定範囲の地域に居住する住民の生命、身体の安全等を個々人の個別的利益として保護しているが、財産権までは保護していない。 |
| パチンコ店の風俗許可を争う周辺住民 (S10.12.17) | × | 風営法は所定の地域に居住する者の個別的利益を保護する趣旨を含まない。 |
| 墓地経営許可を争う付近住民(H12.3.17) | × | |
| 都市計画事業認可を争う周辺住民(H17.12.7) | 被害を直接的に受ける住民は〇 関係地域外に移住する者は× | 被害を直接的に受けるのは事業地の周辺の一定範囲の地域に居住する住民に限られ、その被害の低では、居住地が事業地に近接するにつれて増大するものと考えられる。 |
| 病院開設許可を争う医療施設開設者(H19.10.19) | × | |
| 場外車券販売施設設置許可を争う 周辺病院・周辺一般住民(H21.10.15) | 医療施設等設置者は〇 周辺住民は× | 位置基準は、健全で静穏な環境の下で円滑に業務を行うことのできる利益を、個々の解説者の個別的利益として保護する趣旨をも含む規定。 |
| 特急料金改定認可を争う定期通勤者(H1.4.13) | × | 地方鉄道法21条の趣旨は、もっぱら公共の利益を確保することにある。 |
| 史跡指定解除処分を争う研究者(H1.6.20) | × | 文化財の保存・活用から個々の県民あるいは国民が受ける利益については、公益の中に吸収解消される。 |
以上、15個の判例を覚えるようにしてみてください。本試験で問われる可能性の高い判例には、理由も付しました。
ポイント③:「訴えの利益」に関する判例を覚えましょう。
訴えの利益に関するリーディングケースの判例はありません。以下、様々な事情に応じて個別具体的に判断がなされています。
| 事案 | 訴えの利益 |
|---|---|
| 優良運転者の記載のない運転免許証の更新処分取消訴訟 (H21.2.17) | 〇 |
| 建築工事完了後の建築確認取消訴訟 (H59.10.26) | × |
| 土地改良事業終了後の土地改良事業認可処分取消訴訟 (H4.1.24) | 〇 |
| 強制送還執行後、上陸拒否期間内の退去強制令書発付処分取消訴訟 (H8.7.12) | 〇 |
| 在留資格喪失後の再入国不許可処分取消訴訟 (H10.4.10) | × |
| メーデー経過後の皇居外苑使用不許可処分取消訴訟 (S28.12.23) | × |
| 予備免許執行後の放送局免許処分取消訴訟 (S43.12.24) | 〇 |
| 代替施設整備後の保安林指定解除処分取消訴訟 (S57.9.9) | × |
| 市議会議員立候補後の公務員懲戒免職処分取消訴訟 (H40.4.28) | 〇 |
| 処分後の不利益期間終了後の運転免許停止処分取消訴訟 (S55.11.25) | × |
| 文書図面閲覧禁止の処分終了後の懲罰処分取消訴訟 (S50.10.9) | × |
訴えの利益に関して、試験で判旨が問われることは少ないため、判旨の暗記は不要ですが、事案と結論(訴えの利益の有無)は覚えましょう。
まとめ:処分性、原告適格、訴えの利益毎に体系付けして、判例を暗記しましょう。
いかがでしたでしょうか。行政事件訴訟法の範囲だけでも、約50個も覚えるべき判例があります。
少々大変ですが、基本的な判例は覚えておいて、本番では是非満点を目指しましょう。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければ、他の行政法の「5分で解説シリーズ」もご覧ください。
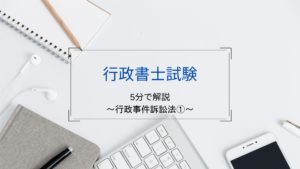
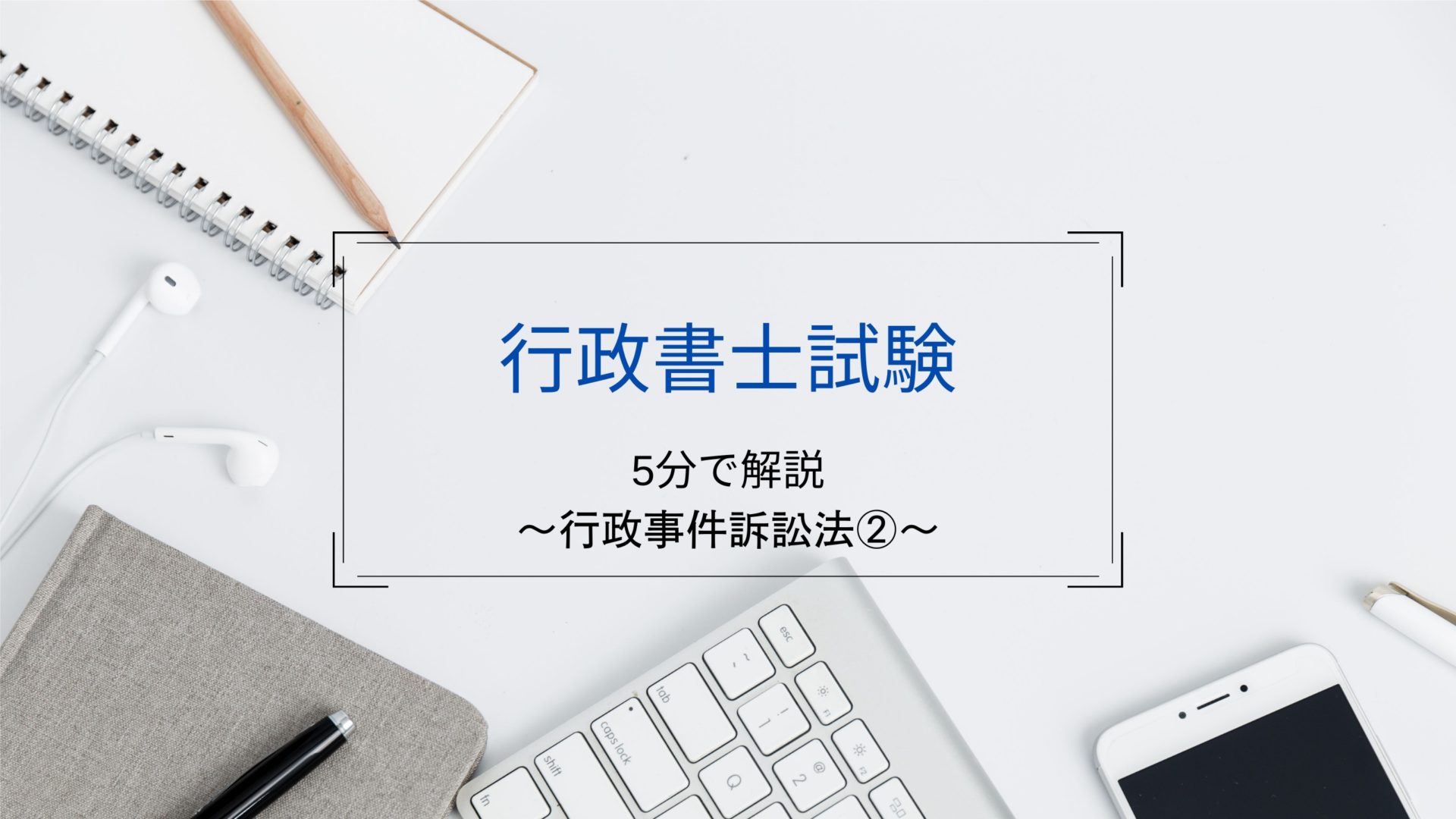
コメント