どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
既にご存じかと思いますが、建設業経理検定(建設業経理士試験)1級には「財務諸表」「財務分析」「原価計算」の3科目があり、3科目に合格して初めて「建設業経理士1級」の資格が与えられます。
これら3科目は同日に受験することも可能ですし、1科目ずつ別々に受験することも可能です。
いずれにせよ、最初の1科目の合格から5年以内(計10回の試験)に全3科目に合格する必要があります。
とはいっても、まだ建設業経理検定の勉強を開始したばかりの段階だと、各科目の試験の難易度や試験範囲が分からないので、どの科目から順番に勉強をすればよいか悩みますよね。
私は2019年9月、建設業経理士1級試験3科目全てに合格することが出来ました。
そんな私が、各科目の難易度を踏まえた上での、科目の勉強順番のおすすめについて解説します。どの科目から勉強すべきか悩んでいる受験生の悩みを解決すべく、本記事を作成させていただきました。
結論:おすすめの勉強順番は『4通り』(学習経験の有無などで異なる。)
まず結論から記載しますが、私のおすすめする勉強順番は以下の通りです。
- 簡単な科目の勉強から始めたい方
(まずは1科目合格を目指す方) : 財務分析→原価計算→財務諸表 - 日商簿記2級または3級の勉強経験がある方 : 原価計算→財務分析→財務諸表
- 難しい科目の勉強から始めたい方 : 財務諸表→原価計算→財務分析
- 同時に3科目の合格を目指す方 : 好きな順番でよい。
以下、各順番の理由を解説していきます。
各科目の難易度(「財務諸表」>「原価計算」>「財務分析」の順に高い。)
3科目合格した私の立場からの意見としては、
一番簡単な科目が「財務分析」で、一番難しい科目が「財務諸表」のように思います。
この難易度の前提で、勉強順番を検討します。
財務分析
3科目の中で一番難易度が低いのが、「財務分析」になります。
私の合格までの勉強時間は、「約50時間」程度でした。
※個人差はあると思いますので、あくまでもご参照までに。
「財務分析」試験では、貸借対照表や損益計算書記載の数字から、会社の財務状況を分析するために、様々な比率を暗記する必要があります。
この覚えるべき比率をまとめたものが、「財務分析主要比率表」になります。
https://www.keiri-kentei.jp/data/pdf/exam/R1B_hiritu.pdf
正直な話、この比率を全て暗記するだけで合格点に達することが出来ます!
暗記が苦手な方は苦労するかもしれませんが、暗記量もそこまで多くはありません。
市販のテキストを比較してみると一目瞭然ですが、3科目のうち財務分析だけ明らかにテキストが薄いです。それくらい、覚える量自体が少ないですね。
本番でも特にひねった問題が出題されず、暗記した比率をもとに、財務諸表から〇〇比率を計算する形式の問題がほとんどです。
基本的に電卓で数字を打ち込めば解ける問題がほとんどです。
よって、財務分析が一番楽です。
『財務分析』の科目の特徴・勉強法について気になる方は↓の記事をご覧ください。
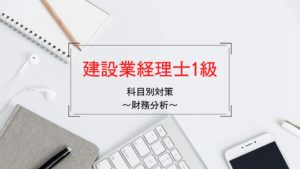
財務諸表
3科目の中で一番難易度が高いのが、「財務諸表」になります。
私の合格までの勉強時間は、「約100時間」程度でした。
財務諸表では、数多くの勘定科目(ex.未成工事支出金、建設仮勘定)を暗記する必要があります。
暗記した上で、仕訳処理(「○月○日、●●を購入した。」といった事実を勘定科目で評価する。)が必要になります。
また、試験問題を大きく大問で分けると5問(第1問~第5問)あり、どの科目の試験も最後の「第5問」が一番配点が高くなっているのですが、この第5問の難易度が一番高いように感じました。
また、財務諸表ならではですが、一問間違えると連鎖的に次の問題を間違えるという形式(※完成工事高自体の算出を間違えると、完成工事高にかかる税金額も当然誤ることになる。)のため、一つミスした、もしくは1つだけ分からないといった場合でも、それだけで4点~6点落としてしまうことになります。
そして、「第2問」で、よくわからない問題が毎回出題される気がします。(私が使っていたテキストには載っていなかった内容が、テストで出題されたこともありました。)
なので、財務諸表が一番難しいのではないかと思います。
『財務諸表』の科目の特徴・勉強法について気になる方は↓の記事をご覧ください。
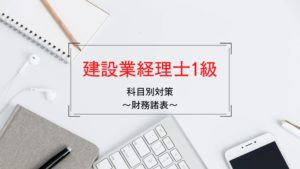
原価計算
財務諸表と財務分析のちょうど中間の難易度に当たるのが「原価計算」です。
私の合格までの勉強時間は、「約100時間」程度でした。
※必要勉強時間は財務諸表と変わっていないですが、私は原価計算から勉強に取り掛かったため、要領が掴めていなかったことが理由です。
原価計算は、暗記自体はそこまで多くはありません。
(計算方法が暗記だとするなら、それなりに多くはなりますが。)
計算式や計算方法を理解して、それに当てはめて問題を解いていくようなイメージです。
ただ個人的に、原価計算は他の2科目と違い試験に癖があると思うので、より過去問を解いておくことが大事になります。
『原価計算』の科目の特徴・勉強法について気になる方は↓の記事をご覧ください。
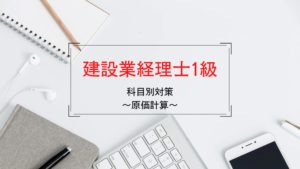
補足:日商簿記試験の勉強経験がある方にとっては、難易度が変わります。
なお、上記の通り、
商業簿記=財務諸表 工業簿記=原価計算 と似て非なる関係にありますので、
「日商簿記3級」の受験経験がある方は、「財務諸表」
「日商簿記2級」の受験経験がある方は、「財務諸表」「原価計算」の必要勉強時間が減ると思います。
試験範囲は、建設業経理士1級の方が日商簿記2級より広いので、勉強しなくても良いということにはならないかと思われます。
具体的に言うと50時間程度は減るイメージです。ですので、必要勉強時間は、以下が目安になります。
建設業経理士1級と日商簿記2級の相関性について気になる方は↓の記事をご覧ください。
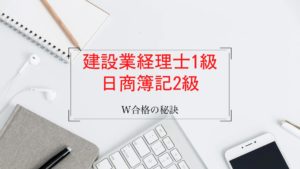
※同時に3科目の合格を目指す方⇒予備校受講がおススメ!
人によっては、3科目同時に合格したい!と考え方もいらっしゃるでしょう。
私は1級に独学で合格出来ましたが、1科目→2科目の順に受験しました。もし3科目同時受験されるなら、予備校講座を受講した方が明らかに効率が良いです。積極的に予備校の受講を検討しましょう。
なお、本ブログでは「Net-school」をおススメしています。以下ボタンより、詳細を確認してみてください。
その他の建設業経理士1級のおすすめ予備校について気になる方は↓の記事をご覧ください。
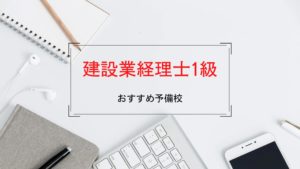
まとめ:試験日から逆算して、勉強計画を立てましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。
もちろん、難易度の感じ方は人それぞれですが、あくまでも参考としていただければと思います。
いずれにせよ、どういうスパンで試験に合格するつもりなのかによって、勉強方針・勉強順が異なります。それを見定めたうえで、試験日から逆算して勉強計画を立てていきましょう!
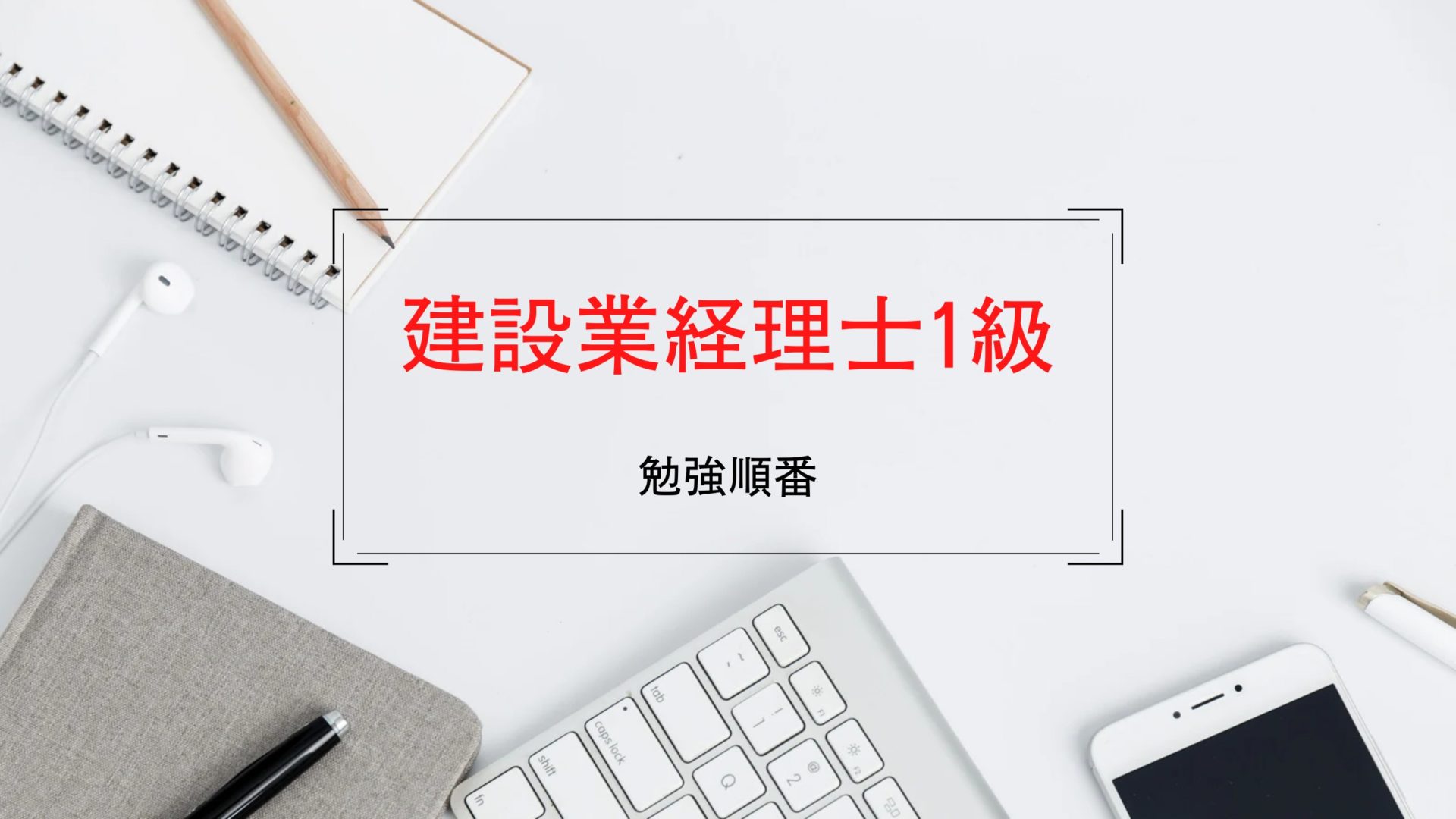
コメント