どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
行政書士試験の法令科目は「法学基礎」「憲法」「行政法」「民法」「商法」の計5科目あります。このうち、民法と行政法の次に重要度が高いのが、憲法です。
行政法や民法ほど重点的に学習する必要はありませんが、全く勉強しないのは危険です。憲法では、効率よく勉強することが大事です。とはいっても、初学者の方は、効率良い憲法の学習方法が分からないのではないでしょうか。
私は、2020年の行政書士試験に独学で一発合格することができました。
そんな私が、本記事にて、憲法の過去問の出題傾向、出題傾向を踏まえた対策方法を解説します。これから憲法の学習を始める方の参考になりますと幸いです。
出題数・配点割合
法令科目の点数内訳と配点割合をまとめたものが以下の表になります。
| 科目 | 5肢選択式 | 配点 | 多肢選択式 | 配点 | 記述式 | 配点 | 合計 | 配点割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎法学 | 2問 | 8点 | 8点 | 3% | ||||
| 憲法 | 5問 | 20点 | 1問 | 8点 | 28点 | 11% | ||
| 行政法 | 19問 | 76点 | 2問 | 16点 | 1問 | 20点 | 112点 | 46% |
| 民法 | 9問 | 36点 | 2問 | 40点 | 76点 | 31% | ||
| 商法 | 5問 | 20点 | 20点 | 8% | ||||
| 合計 | 40問 | 160点 | 3問 | 24点 | 3問 | 60点 | 244点 | 100% |
行政書士試験は全部で60問出題されますが、このうち憲法は計6問(5肢選択式から5問、多肢選択式から1問)出題されます。
法令科目の合計は244点ですが、そのうち11%を憲法が占めています。
過去5年分の出題範囲(5肢選択式・多肢選択式)
過去5年分の憲法の試験範囲を以下の表にまとめました。
| No. | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問題3 | 国務行為 | 議員 | 身体の自由 | 国家賠償法・ 損失補償 | 表現の自由 |
| 問題4 | 学問の自由 | 法の下の平等 | 表現の自由 | プライバシー権 | 営業の自由 |
| 問題5 | 生存権 | 選挙権・選挙制度 | 信教の自由 | 適正手続 | |
| 問題6 | 選挙 | 教科書検定制度 | 衆議院議員の 解散 | 国会 | 内閣 |
| 問題7 | 裁判官の身分保障・ 表現の自由 | 違憲性の主張適格 | 法の一般原則 | 裁判の公開 | |
| 問題41 | 公務員の 政治的自由 | 報道の自由 | 労働組合の統制権と 政治活動の自由 | 裁判員制度の 合憲性 | 法律上の訴訟 |
憲法の試験範囲は、「総論」「人権」「統治」の3つの分野に大分できますが、上記の表の通り、毎年、「人権」と「統治」分野から多く出題されているのが特徴です。
そのため、「人権」と「統治」の分野をメインに学習しましょう。
勉強法:愚直に「判例」と「条文」を覚えるべき。
憲法は、基本的に判例と条文からの出題がほとんどです。
特に、憲法の中での人権分野は「判例」が、統治分野では「条文」が大事です。また、多肢選択式では、判例中の細かい文言が問われます。そのため、とにかく「判例」と「条文」を正確に理解することを心がけましょう。
以下、出題が多い人権分野と統治分野の勉強法を解説します。
人権分野:「判例」を細かく読み込む。
人権分野では、判例からの出題がほとんどです。判例六法などに掲載のある判例は、全て覚えるようにしましょう。
※多肢選択式対策も兼ねる。
多肢選択式問題の1問は憲法から出題されます。出題形式は「判旨の空欄補充」が定着しています。
判旨中の細かい文言が出題されますので、判例の重要判旨と結論だけ覚えたのでは多肢選択式の問題が解けるようになりません。
もっとも、多肢選択式では、見たことのない判例や裁判例が出題されることが多いです。実際、私が受験した2020年試験でも、見たことのない判例が出題され、戸惑いました。
見たことがない判例でも、お手上げになる方が多いのではないかと思います。ただ、全く知らない判例だったとしても、判示される言葉じりは、他の判例や裁判例で用いられているものもあります。そのため、本番である程度選択肢を絞ることができるようになります。
このように、判例に慣れておくことができれば、多肢選択式で高得点をとりやすいです。
統治分野:試験直前期に丸暗記でOK。
統治分野の場合、判例が少ない代わりに、条文知識を問われる問題が多く出題されます。なので、統治の分野では、該当の条文(41条以降の条文)をできるだけ暗記しましょう。
もっとも、「条文」を暗記するのは直前期でOKです。なぜなら、すぐ忘れがちだからです。統治の条文は抽象的で、内容の理解が難しいので、日常学習で統治の条文を勉強したとしても、本番では記憶から抜けてしまうことが多いです。
憲法の条文は全部で99条しかなく、また各条文自体も短いため、試験直前期に詰め込んで丸暗記しても本番には間に合います。
得点目標:憲法は28点中「18点」は獲得したい。
憲法の問題の難易度の試験範囲の広さを考慮すると、合計28点分のうち18点は獲得すべきと考えています。
5肢選択式が4点、多肢選択式で8点(1問2点分:計4問)なので、5肢選択肢は3/5問、多肢選択式は3/4問正解するのが理想です。
70%〜80%は正解できる程度の学習をしておきましょう。
なお、私がおすすめする本番の得点目標は、↓の記事で紹介しております。
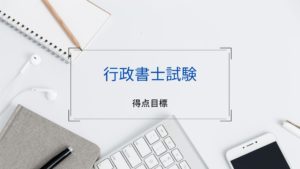
まとめ:判例は日常学習で細かく読み込む。条文は直前期に詰め込む。
以上憲法の学習方法を紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
判例は普段の学習に取り入れ、細かい文言まで読み込みましょう。また、条文は、直前期に丸暗記するようにしましょう。
憲法は比較的点数のとりやすい科目ですので、ぜひ得点源になるといいですね。
他の法令科目の勉強法も別記事にて解説しておりますので、併せてご覧ください。
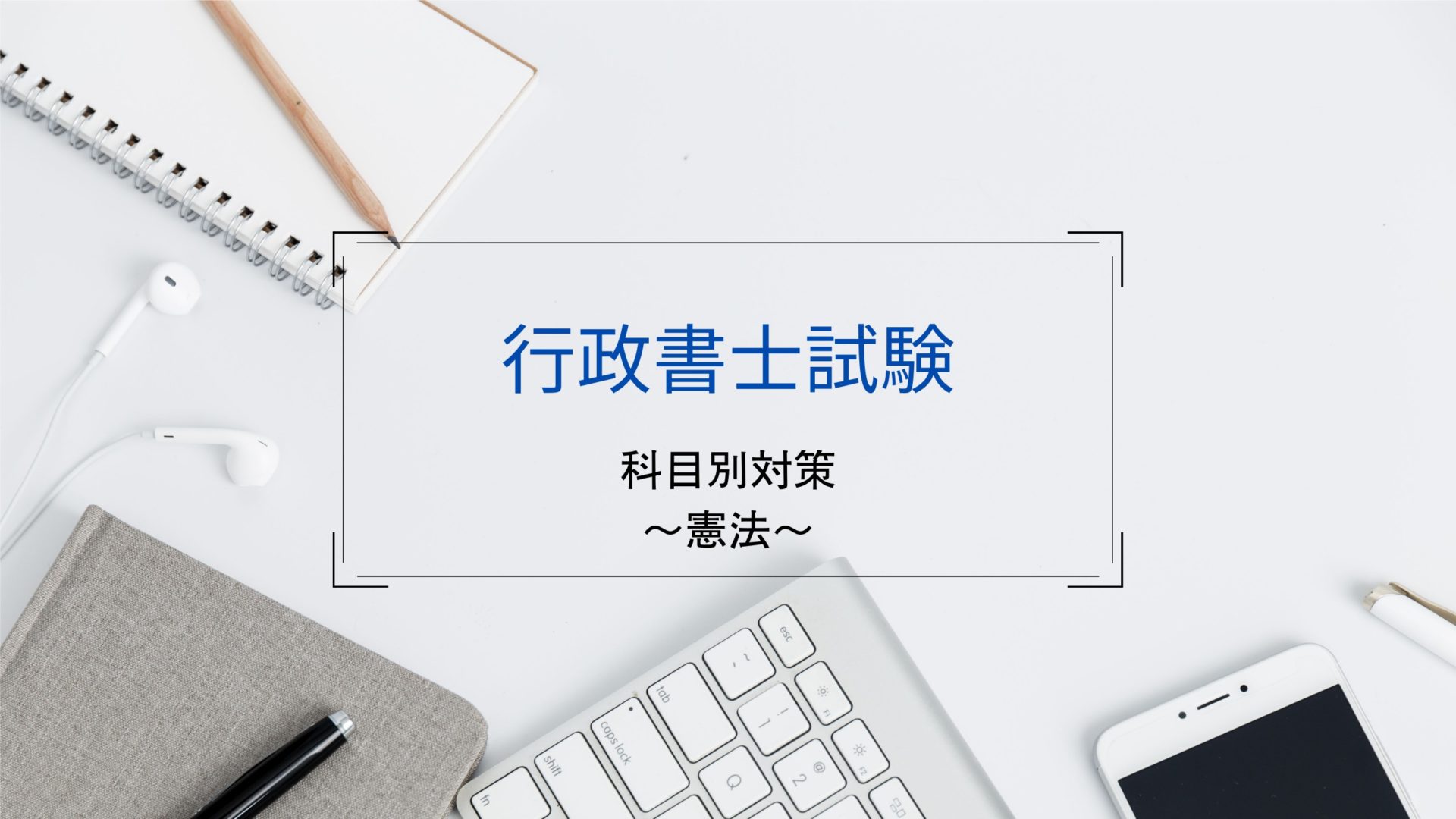
コメント