どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
行政書士試験は、一般知識科目があるなど、試験科目が非常に広い試験です。科目ごとに足切りはあるもののそこまで厳しくはないため、得点を取る科目・捨てる科目などを作っても合格できます。
行政書士試験の合格基準点は6割(300点中180点)に設定されています。合格点に変動はなく、試験の難易度の変化は毎年少ないので、事前に、科目ごとの目標点を決めておいた方がよいです。

私は、2020年行政書士試験を受験した際、事前に科目ごとの目標点を決めて臨み、無事合格できました。
そこで、本記事では、私の考える理想的な目標得点割合を紹介します。参考になりますと幸いです。
理想の点数配点
結論から言ってしまいますが、私の考える理想の目標得点は以下の通りです。
| 大区分 | 小区分 | 出題形式(問題番号) | 問題数(配点) | 目標点/配点 | 得点割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法令等 | 基礎法学 | 5肢選択式(1・2) | 2問(1問4点) | 4/8 | 50%(1問) |
| 憲法 | 5肢選択式(3~7) | 5問(1問4点) | 12/20 | 60%(3問) | |
| 多肢選択式(41) | 1問(1問8点) | 6/8 | 75% | ||
| 行政法 | 5肢選択式(8〜26) | 19問(1問4点) | 60/76 | 約80%(15問) | |
| 多肢選択式(42・43) | 2問(1問8点) | 12/16 | 75% | ||
| 記述式(44) | 1問(1問20点) | 10/20 | 50% | ||
| 民法 | 5肢選択式(27~35) | 9問(1問4点) | 28/36 | 約80%(7問) | |
| 記述式(45・46) | 2問(1問20点) | 20/40 | 50% | ||
| 商法・会社法 | 5肢選択式(36~40) | 5問(1問4点) | 4/20 | 20%(1問) | |
| 一般知識 | 5肢選択式(47~60) | 14問(1問4点) | 24/56 | 約40%(6問) | |
| 180/300 | 60% |
「学習必須科目」と「学習すべき科目」と「捨て科目」
各科目の優先勉強度について、私は以下のように区分しています。
- 学習必須科目:憲法、行政法のうち行政手続法・行政不服審査法・行政事件訴訟法・国家賠償法、民法
- 時間があれば学習すべき科目:商法・会社法、地方自治法
- 捨てても良い科目:基礎法学、行政法のうち総論部分、一般知識
学習必須科目については正答率60%〜80%程度、
捨てても良い科目については正答率20%〜50%程度、
記述式は50%程度正解できれば、180点取れる計算になっています。
確実に合格できるレベルに到達したい方は、必要に応じて、「商法・会社法」や「地方自治法」をしっかり勉強すればOKです。
各科目ごとの学習方針について
憲法(5肢選択式+多肢選択式)
憲法は判例の細かい文言まで問われることが多く、難易度が高いので、まずは5肢選択式で5問中3問、多肢選択式で4問中3問程度正解することを目標としましょう。
憲法については、人権分野は判例の学習、統治分野は条文の学習がメインです。日常の学習においては、いずれも、細かい文言まで押さえることを意識しておいて下さい。
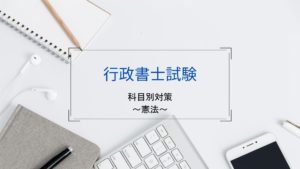
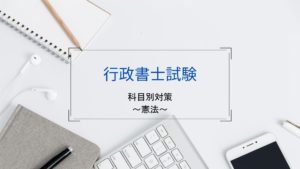
行政法(5肢選択式+多肢選択式)
5肢選択式は全部で19問出題されますが、このうち「行政手続法」「行政不服審査法」「行政事件訴訟法」「国家賠償法」の範囲から、最低でも11問出題されます。これらの科目は、他の行政法分野と比較して難易度が低く点数が取りやすいので、できれば満点を目指しましょう。
その他の8問のうち4問程度は正解できるとして、行政法全体で15問/19問は取っておきたいです。
多肢選択式の問題も、で4問中3問程度(75%)は正答しておきたいところです。
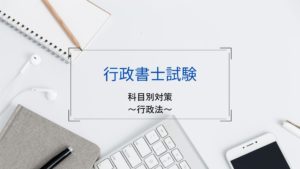
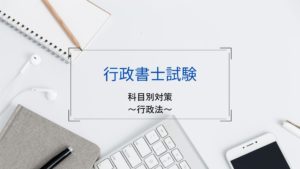
行政法(記述式)
50%を獲得したいところです。
苦手意識を感じている方も多いかもしれませんが、50%程度得点することはそこまで難しくありません。
日常の学習から、選択式と記述式のどちらにも対応できるような勉強方法を心がけましょう。
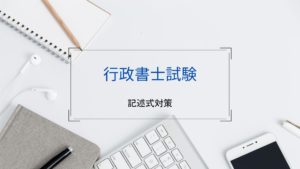
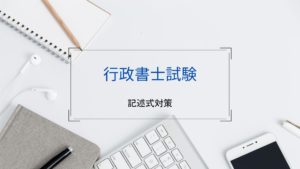
民法(5肢選択式)
民法は条文自体が多く、出題範囲も広いため、難易度は高いです。ただ、民法は差がつく科目であり、実務でも生きる法律ですので、9問中7問(約80%)は正解したいところです。



ちなみに、私は5/9問しか正解できていませんでしたが、合格できました。
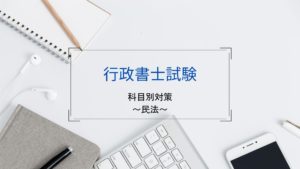
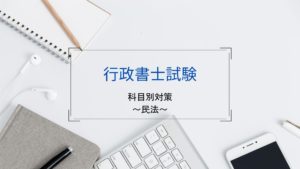
民法(記述式)
前述の通り、記述式は50%獲得したいところです。日常の学習から、選択式と記述式のどちらにも対応できるような勉強方法を心がけましょう。
商法・会社法(5肢選択式)
商法・会社法は、条文数が民法とほぼ同じ数あり、出題範囲がかなり広いにもかかわらず、本番では5問しか出題されません。要するに、勉強するにはコスパが悪い科目です。
ですので、5問中1問正解でOK、という甘めの目標点にしております。他の科目を勉強を一通り終えて、商法・会社法にまで取り掛かる余裕がありそうであれば、学習しましょう。
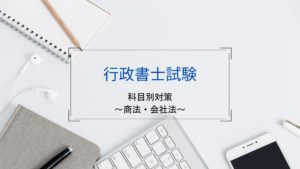
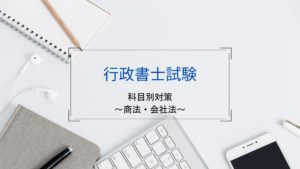
一般知識(5肢選択式)
一般知識は、足切りにかからなければそれでよいと思っておりますので、足切りギリギリの14問中6問という点数を設定しています。
足切りにかからないよう、特に本番での問題の解き方に注意しましょう。
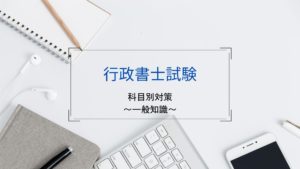
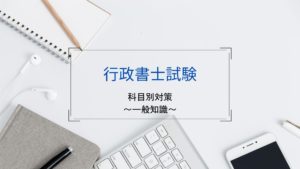
まとめ:憲法・行政法・民法で「7割」獲得し、一般知識で「足切り」にかからなければ受かる試験です。
はい、いかがでしたでょうか。
行政書士試験は、メインの憲法・行政法・民法の3科目で7割程度獲得できるようになれば、他の分野の点数が低くても合格しやすいです。
まずはメインの3法の知識を固め、必要に応じてその他の科目の勉強にも取り掛かりましょう。
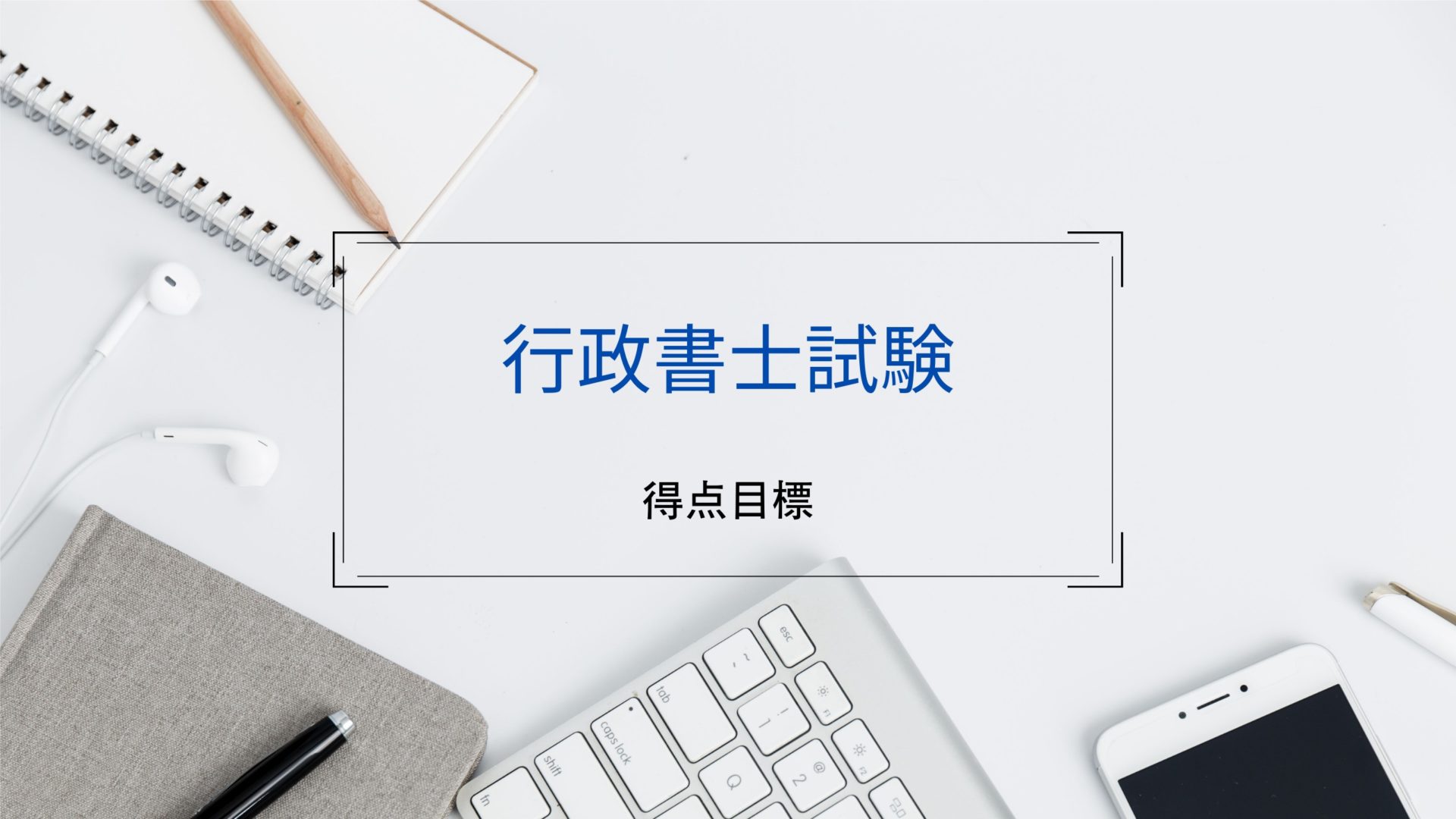
コメント