どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
行政書士試験の法令科目は「基礎法学」「憲法」「行政法」「民法」「商法」の5科目です。このうち、一番難易度が高いとされているのが民法です。
理由としては、民法の条文は約1000条あるため試験範囲が広いこと、試験範囲の中から満遍なく出題されるため、ヤマを張りにくいことにあります。
これから民法の勉強を始める方、または現に始めた方でも、民法の学習に挫折しそう、と感じる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
私は、2020年の行政書士試験に独学で一発合格することができました。
そんな私が、本記事にて、民法の過去問の出題傾向、出題傾向を踏まえた対策方法を解説します。民法に苦手意識を感じている方の参考になりますと幸いです。
出題数・配点割合
法令科目の点数内訳と配点割合をまとめたものが以下の表になります。
| 科目 | 択一式 | 配点 | 選択式 | 配点 | 記述式 | 配点 | 合計 | 配点割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎法学 | 2問 | 8点 | 8点 | 3% | ||||
| 憲法 | 5問 | 20点 | 1問 | 8点 | 28点 | 11% | ||
| 行政法 | 19問 | 76点 | 2問 | 16点 | 1問 | 20点 | 112点 | 46% |
| 民法 | 9問 | 36点 | 2問 | 40点 | 76点 | 31% | ||
| 商法 | 5問 | 20点 | 20点 | 8% | ||||
| 合計 | 40問 | 160点 | 3問 | 24点 | 3問 | 60点 | 244点 | 100% |
行政書士試験は全部で60問出題されますが、そのうち民法からは計11問(5肢選択式から9問、記述式から2問)出題されます。
法令科目の合計は244点ですが、そのうち31%を民法が占めています。
過去5年分の出題範囲(5肢選択式・記述式)
過去5年分の民法の試験範囲を以下の表にまとめました。
| 5肢選択式 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問題27 | 公序良俗 | 事項の援用 | 制限行為能力者 | 意思表示 | 虚偽表示 |
| 問題28 | 付款 | 代理 | 占有改定 | 失踪 | 占有権 |
| 問題29 | 不動産物権変動 | 動産物権変動 | 根抵当権 | 物権的請求権 | 根抵当権 |
| 問題30 | 抵当権 | 担保物権 | 選択権 | 留置権 | 債務不履行 |
| 問題31 | 弁済 | 質権 | 債務引受 | 債務不履行 | 契約解除 |
| 問題32 | 使用貸借・賃貸借 | 転貸借契約 | 同時履行の抗弁権 | 債権者代位権 | 賃貸借契約 |
| 問題33 | 不法行為各論 | 事務管理 | 賃貸借契約 | 契約不適合責任 | 法定利率 |
| 問題34 | 離婚 | 不法行為 | 不法行為 | 不法行為 | 不法行為 |
| 問題35 | 後見 | 氏 | 特別養子縁組 | 共同相続 | 相続 |
民法の試験範囲は、「総則」「物権」「債権総論」「債権各論(不法行為)」「親族」の5つの分野に大分できますが、上記の表の通り、毎年、各分野から最低1問は必ず出題されており、出題傾向に偏りがないのが特徴です。
試験範囲の全体から満遍なく出題されるため、ヤマを張ることはできません。
| 記述式 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問題45 | 制限行為能力者 への催告 | 共有 | 第三者詐欺 | 債権譲渡 | 相続による 追認可否 |
| 問題46 | 贈与 | 第三者のために する契約 | 背信的悪意者 | 不法行為 | 債権者代位権 |
記述式の問題でも、過去5年間で同じ範囲からの出題がなく、出題範囲が読めません。
勉強法:愚直に「条文」と「判例」を覚えるべき。
試験範囲が広いため、民法の勉強に近道はなく、安定して高得点を取るには全範囲を満遍なく学習する必要があります。試験の問題も難易度も高く、条文・判例を正確に理解できていないと解けない問題が多いです。
そのため、とにかく「条文」と「判例」を正確に理解することを心がけましょう。
民法から法令科目の学習を始めた方の場合は、いきなり躓く可能性もありますが、逆にいえば、民法の学習を終えると、他の法令科目の学習が楽に感じます。
1番肝になる分野なので、根気強く学習しましょう。
得点目標:民法は選択式70%~80%、記述式で50%得点したい。
民法は難易度が高いですが、私は、選択式で70~80%、記述式で50%を目標とすべきと考えています。
難易度は高いのですが、商法・会社法などに比べると配点のウェイトが高いので、民法で高得点を取ることができると合格に近づきます。
なお、私がおすすめする本番の得点目標は、↓の記事で紹介しております。
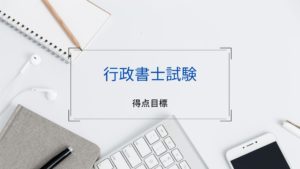
まとめ:近道はないので、こつこつと勉強しましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。
民法の学習が一番大変ですが、民法で高得点を取ることができると、合格にかなり近づきます。難易度が高い分野ですが、粘り強く勉強しましょう。
他の法令科目の勉強法も別記事にて解説しておりますので、併せてご覧ください。
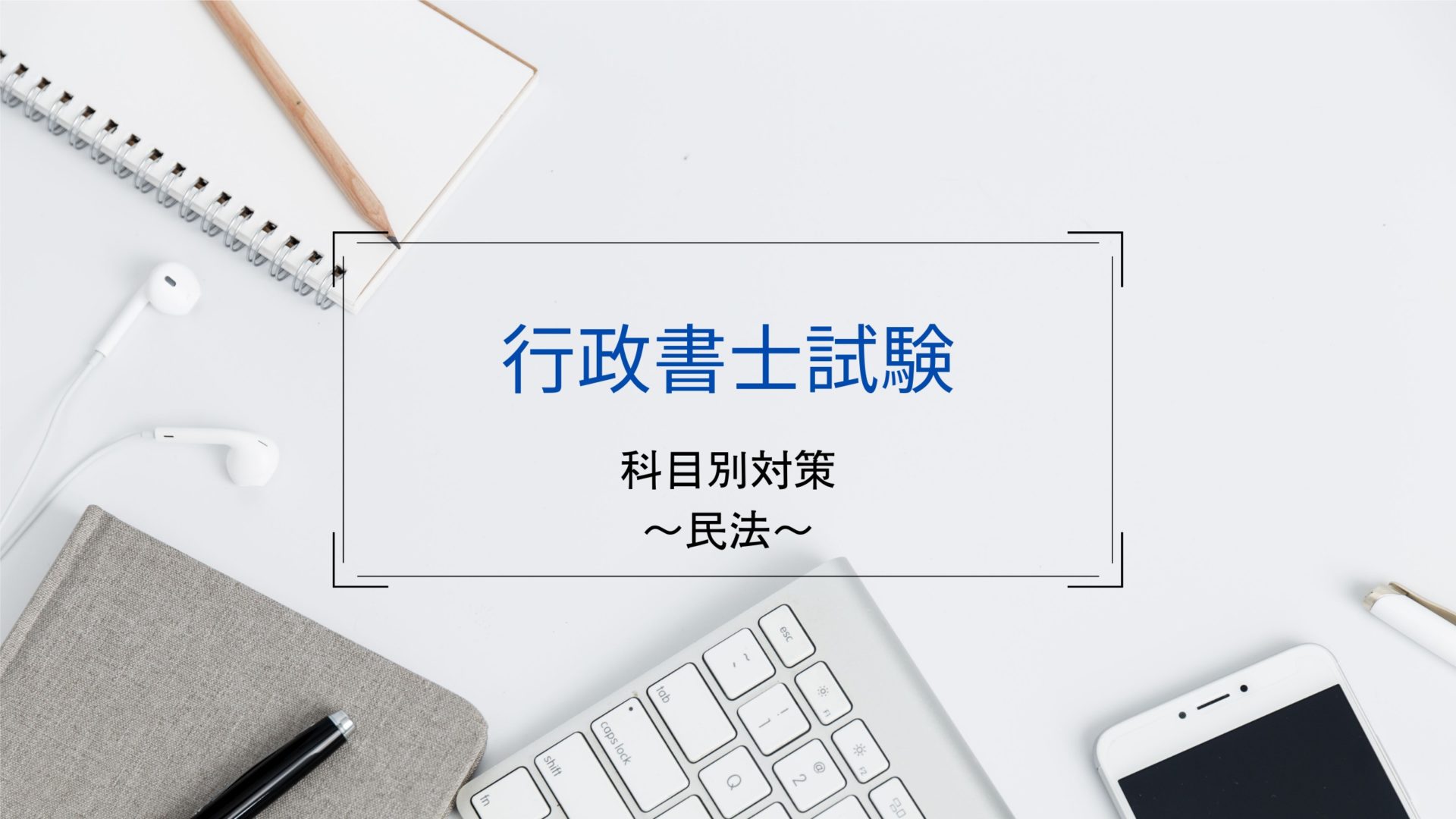
コメント