どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
行政書士試験の科目は、大きく「法令科目」と「一般知識科目」の2つに分類され、それぞれに足切り基準があります。出題数も多く差がつく分野である法令科目メインに勉強するのが当然ですので、一般知識の勉強が疎かになりがちです。一般知識の方が足切りに引っかかってしまう可能性が高くなります。
一般知識は足切りにかからない程度に最低限勉強すればOKなのですが、一般知識対策としてどういう勉強をすれば良いのか、悩んでいる受験生も多いのではないのでしょうか。
一般知識の勉強にかける時間が取れなかったわけではないです。試験の前に各分野の得点目標を決めましたが、一般知識の勉強にかける時間はゼロでも大丈夫という根拠があったからです。
本記事では、一般知識の学習の必要性、勉強する場合の具体的な勉強方法について、合格者の観点から解説します。一般知識対策に悩む受験生の参考になりますと幸いです。
一般知識等科目の出題範囲・足切り基準
まず、行政書士試験の3つの足切り基準について、確認しておきましょう。
- 行政書士の業務に関し必要な「法令等科目」の得点が244点中122点(50%)以上
- 行政書士の業務に関連する「一般知識等科目」の得点が56点中24点(約40%)以上
- 「試験全体」の得点が300点中180点(60%)以上
「一般知識等科目」の足切り基準は、6/14です。(毎年変わりません。)
「一般知識等科目」の出題範囲・割合は以下の通りです。
- 政治・経済・社会 から7問
- 情報通信・個人情報保護 から4問
- 文章理解 から3問
結論:足切りにかからない、ギリギリの点数を目指せ。
一般知識の得点目標ですが、私は、一般知識科目は6割ギリギリ取れれば問題ないと考えています。
なぜなら、費用対効果が悪いからです。
「政治・経済・社会」に関しては、試験範囲が広い上に、時事問題も多く出題されるので、予備校のテキスト等で学習したとしても本番での得点UPに繋がらない可能性が高いです。「情報通信・個人情報保護」に関しては、ITの問題なども多く、行政書士試験合格のためにあまり時間をかける分野ではないような気がしています。
一般知識よりは、憲法・行政法・民法などの法令科目を勉強した方が、得点UPに確実に結び付きます。
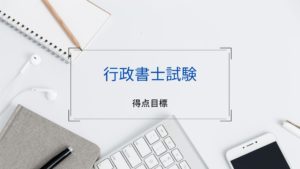
どのような配分で、6問正解するか?
足切り基準は6/14なので、最低でも6問正解する必要がありますが、個人的な理想の正答率は以下の通りです。
- 政治・経済・社会 7問中 2〜3問正解
- 情報通信・個人情報保護 4問中 1〜2問正解
- 文章理解 3問中 2〜3問正解
6問ギリギリ正解の前提で作成しておりますが、これを1つの基準として考えていただければと思います。
分野別では、3 文章理解>2 情報通信>1 政治・経済・社会の順で、得点しやすいです。文章理解で確実に2問できれば、無勉強でも残り11問中4問得点できればOKですが、知っている問題が出題されることもあるので、意外と4点は簡単に取れます。
なので、(極論ではありますが、)合格のために一般知識対策は不要なのではないかと考えております。
とは言っても、無勉強は怖い、と考える方も当然いらっしゃるでしょう。そこで、一般知識を対策するとした場合の学習上のポイントについて、私が解説します。
文章理解(問58~問60)
問題58〜問題60は、文章理解の問題です。著作権の関係からHP上に過去問が掲載されていませんが、基本的に長文読解(国語)の問題です。
- 空欄にあてはまる正しい語彙を選ぶ。
- 空欄にあてはまる正しい文を選ぶ。
- 正しい文章となるよう、文を並び替える。
という趣旨の問題が出題されます。
「全く問題が分からない。」ということはないと思いますし、じっくり読めば誰でも解答できる問題ではないかと思います。(正解率もかなり高いと思われます。)
ですので、「文章理解」では、確実に点を取っておきたいところです。出来れば3問、最低でも2問は正解したいですね。
なお、文章理解の難易度は低いですが、解答には時間がかかります。時間切れで回答できない、という事態だけは避けたいので、試験が始まって一番先に解くのがおすすめです。
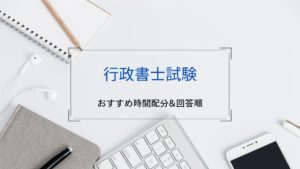
情報通信(問54~問57) ※令和2年度は3問(問55~57)のみ。
情報通信は、個人情報やITに関する問題が多く出題されます。
一般知識を勉強するとした場合、「情報通信」の分野から勉強するのがおすすめです。個人情報に関する問題は、法令科目の「行政法」の試験範囲にも内容が若干絡む場合もあり、理解しておくと行政法の理解にもつながります。
情報通信で2問正解出来たら、ほぼ足切りからは逃れられると思います。
政治経済社会(問47~問53) ※令和2年度は8問(問47~54)。
政治経済社会に関してですが、私は全く勉強しておりませんでした。正直なところ、今でも試験範囲を正確に理解していないですが、対策不要でOKです。
政治経済社会分野の問題の難易度は比較的高めですが、比較的優しい問題が毎年何問か出題されます。そういった問題を確実に得点できるようになりたいですよね。
私が受験した2020年度試験だと、サブスクリプションに関する問題(問52)が、優しい問題のように感じました。話題の「サブスクリプション」がなにかが分かっていれば、正解できる問題でした。
おすすめのテキスト(一般知識用)
参考までに、一般知識を勉強するとした場合のおすすめテキストを1冊紹介しておきます。
Wセミナー出版の「一般知識が得意になる本」です。一般知識分野に関して分かりやすく説明されており、理解が深まります。
まとめ、一般知識で「足切り」とならない程度の学習をしましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。
「法令等に関する科目」の勉強が最優先なので、とにかく民法・行政法といった法律科目を優先的に勉強して安定的な高得点を目指し、一般知識は足切りとならない程度に学習しましょう!
一般知識は、とにかく「文章理解」で確実に得点することをも目標に、あとは運で対応しましょう!(不安な方は「情報通信」を勉強しましょう。)
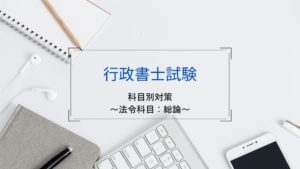
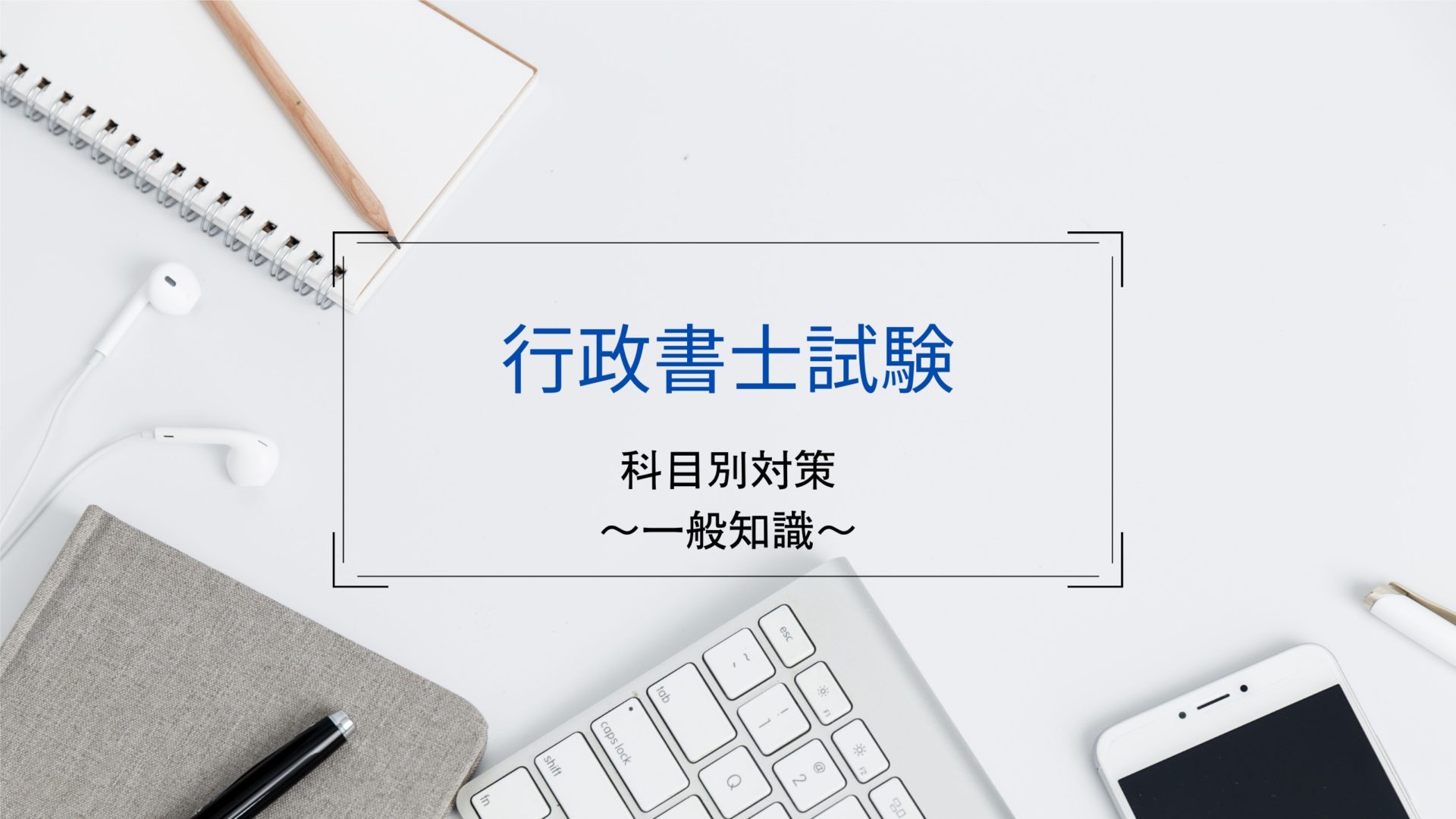

コメント