どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
建設業経理検定1級は、「財務諸表」「財務分析」「原価計算」の3つの科目があり、3科目全部に合格して初めて「建設業経理士1級」の資格が与えられます。
本記事では、「財務分析」に関して、対策のポイント・勉強方法・おすすめのテキストなどについて紹介していきます。
財務分析の勉強法について悩んでいる方にとって、本記事が参考になりますと幸いです。
難易度:3科目の中で1番低い。
私は、建設業経理士1級の3科目(「財務諸表」「財務分析」「原価計算」)の中で、財務分析が1番難易度が低いと考えています。なぜなら、3科目のうちで1番試験範囲が狭いからです。
建設業経理士1級・2級の試験範囲は、公式HPに掲載の「出題区分表」から確認できます。
https://www.keiri-kentei.jp/data/pdf/exam/R5A_kubun_12.pdf
この出題区分表は全部で7pありますが、財務分析の試験範囲は0.5p分しか記載されていません。
出題区分表からしても、試験範囲はもっとも狭いと考えてOKです。
また、財務分析のテキストが3科目の中で1番薄いことが多く、勉強時間も比較的少なくて済みます。そのため、1科目ずつ確実に合格を目指したい方は、まずは財務分析から受験するのがオススメです。
ただし、日商簿記の試験範囲と被らない。
建設業経理士試験の勉強を始める前に、既に同じ簿記系の試験である「日商簿記2級」や「日商簿記3級」の学習経験がある人もいらっしゃるかと思います。特に「建設業経理士」と「日商簿記2級」とは試験範囲が類似しており、学習内容が被っている部分が多いです。
日商簿記2級の試験範囲は、大きく「商業簿記」と「工業簿記」の2つに分けられます。このうち「商業簿記」は「財務諸表」と、「工業簿記」は「原価計算」との相関性が高いです。
しかし、「財務分析」は日商簿記2級と試験範囲との被りがありません。財務分析は、日商簿記の勉強経験がある方でも1から勉強することになるので、日商簿記経験者は財務分析の勉強時間が1番短くことはありません。
※日商簿記との相関性も踏まえた、3科目の勉強順番のおすすめに関しては、↓の記事で詳細に解説しております。

過去問の出題傾向
過去5回分の過去問の出題範囲をまとめたものが以下の表になります。
| 受験回 | 第30回 (2022年3月) | 第31回 (2022年9月) | 第32回 (2023年3月) | 第33回 (2023年9月) | 第34回 (2024年3月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1問 (20点) | 外部分析 | 収益性分析 (対完成 工事高比率) | 総合評価 の手法 | 成長性分析 | 流動性分析 |
| 第2問 (15点) | 建設業の特性 | 総合問題 | 生産性分析 | 収益性分析 | 総合問題 |
| 第3問 (20点) | 各比率の計算 | 各比率の計算 | 各比率の計算 | 各比率の計算 | 各比率の計算 |
| 第4問 (15点) | 収益性分析 | 生産性分析 | 収益性分析 | 生産性分析 | 収益性分析 |
| 第5問 (30点) | 各比率の計算 安全性分析 | 各比率の計算 安全性分析 | 各比率の計算 収益性分析 | 各比率の計算 活動性分析 | 各比率の計算 生産性分析 |
頻出分野を赤字で記載いたしました。財務分析は、以下の5つの分析方法からの出題が大半を占めます。
- 収益性分析
- 安全性分析
- 活動性分析
- 生産性分析
- 成長性分析
なお、第3問と第5問の「各比率の計算問題」は、貸借対照表または損益計算書から、これら5つの分析を行うために必要な数字を探した上での主要比率の計算方法を問うもので、各分析の計算式を暗記することができれば解くことができます。
勉強方法:とにかく、「主要比率」を覚えましょう。
過去問の出題傾向を見て分かる通り、「収益性分析」「安全性分析」「活動性分析」「生産性分析」「成長性分析」からの出題がほとんどです。この5つの分析方法を理解しておけば、試験範囲をほぼカバーすることができます。
5つの分析方法に関する暗記すべき比率は、公式HP↓掲載の「財務分析主要比率表」に記載されており、この比率を正確に理解&暗記するだけで、合格できます。
https://www.keiri-kentei.jp/exam/scope.html
「暗記がつらい…。」と思うかもしれませんが、ボリュームはわずかPDF3ページ程しかなく、そこまで苦ではありません。(財務諸表と比べても全然少ないです。)各分析方法の内容に関連付けて、比率及び比率を用いる根拠を正しく暗記しておきましょう。
補足:おすすめのテキスト・電卓・予備校
ここから、財務分析のおすすめテキスト・電卓・予備校を教材を紹介します。
おすすめのテキスト(計3冊)
基本テキスト・問題集・過去問題集のおすすめを紹介します。
スッキリわかる 建設業経理士1級 財務分析(TAC)
必要な知識のインプットのための基本テキストは、こちらのテキストが一番のおすすめです。
他科目と比較すると分量が薄く、比較的短時間で読了できます。
スッキリとける問題集 建設業経理士1級 財務分析(TAC)
問題集の候補は、このテキストほぼ一択になります。
合格するための過去問題集 建設業経理士1級 財務分析(TAC)
過去問集の候補は、このテキストほぼ一択になります。
※その他、本記事で詳細しきれなかったテキストついては、↓記事にてレビューしております。
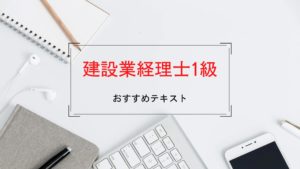
おすすめ予備校
予備校は、Net-schoolがおススメです。
※その他の予備校の講座に関して、↓記事にて紹介しております。
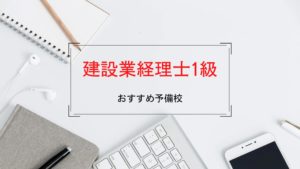
おすすめ電卓
特に財務分析は、電卓選びが重要になります。
電卓はCASIOの「JS-20WKA」がおススメです。(個人的にはシルバーが好きです。)
※電卓に関するレビュー記事は↓
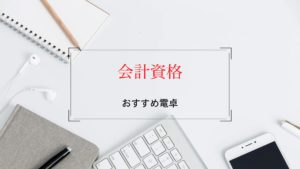
まとめ:とにかく比率を暗記しましょう。(正直、これだけで合格できます。)
はい、いかがでしたしょうか。
繰り返しになりますが、財務分析は、とにかく「財務分析主要比率表」に掲載されている比率を全て覚えるだけで合格が可能な科目です。
まずは、主要比率表の項目を確実に覚えることから始めましょう。
※他2科目対策の記事は↓よりご覧ください!
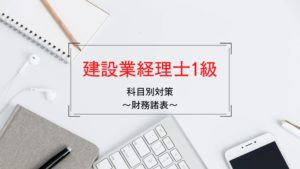
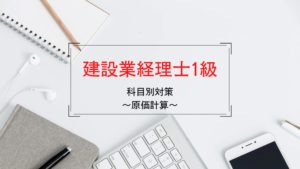
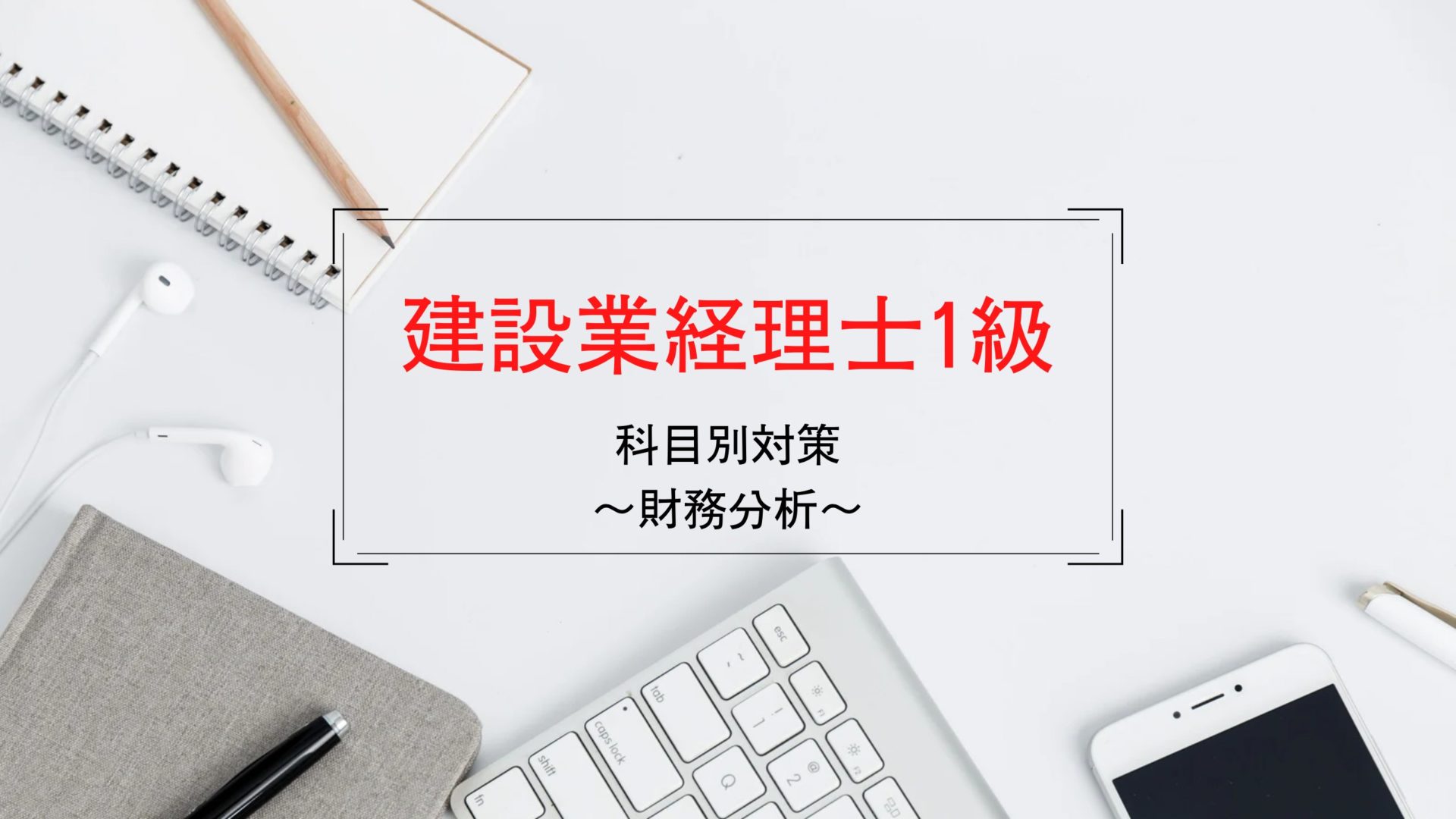




コメント