どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
皆さんご存じの通り、建設業経理検定1級は、「財務諸表」「財務分析」「原価計算」の3つの科目があり、3つの試験に合格して初めて、「建設業経理士1級」の資格が与えられます。
本記事では、3科目の中の「原価計算」の対策のポイント・勉強方法・おすすめのテキストなどを紹介していきます。
原価計算の対策について知りたい方にとって、少しでも参考になりますと幸いです。
原価計算の難易度:3科目の中で1番難しい。
原価計算は、3科目の中で1番難しいです。
原価計算とは、その名の通り、原価の具体的な算定方法を問う科目です。
財務諸表や財務分析は、いわゆる「商業簿記」に近く、具体的な仕訳や、財務諸表を用いた分析方法が問われるのに対し、原価計算はいわゆる「工業簿記」に近く、複雑な計算問題が出題されます。
試験範囲は、試験実施団体のHPに掲載されております。PDFの、第2~第15の範囲です。
https://www.keiri-kentei.jp/data/pdf/exam/R5B_kubun_12.pdf
ご覧いただけると分かりますが、試験範囲はそれなりに広いため、念入りの対策が必要になります。試験範囲は、「材料費」や「労務費」などの費用の内訳に関する分野と、「総合原価計算」「個別原価計算」などの原価計算の方法に関する分野の2種類に分類できます。
また、広い試験範囲に加え、本番では複雑な計算問題が問われます。計算を苦手としている受験生が多いことから、原価計算の難易度は低いです。
過去問の出題傾向
以下の表にて、過去5回分の設問別の出題範囲をまとめてみました。
| 受験回 | 第30回 (2022年3月) | 第31回 (2022年9月) | 第32回 (2023年3月) | 第33回 (2023年9月) | 第34回 (2024年3月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1問 (20点) | 原価計算の目的 | ・実行予算 ・設備投資の 経済性 | 原価計算制度 | 事前原価の種類 予定配賦法の意義 | ・建設業原価計算の目的 ・2つの経費の相違点 |
| 第2問 (10~14点) | 個別原価計算と 総合原価計算 | 原価計算基準 | 配賦方法 | 品質コスト | 経営意思決定の 特殊原価分析 |
| 第3問 (12~18点) | 部門配賦 | 副費配賦 | 損料計算 | 部門配賦 | 車両費配賦額 の計算 |
| 第4問 (16~20点) | 設備投資の経済性 | 正味現在価値 計算 | 設備投資の経済性 | 設備投資の経済性 | 設備投資の経済性 |
| 第5問 (34~40点) | 原価報告書作成 | 原価報告書作成 | 原価報告書作成 | 原価報告書作成 | 原価報告書作成 |
第5問を除き、出題範囲にばらつきあり。
上記の通り、原価計算は、広い出題範囲から幅広く出題されます。比較的「正味現在価値計算」や「損料計算」に関する問題が出題される傾向ではありますが、それでもヤマを張るのは危険です。試験範囲全体を満遍なく学習しておきましょう。
ただ、他の科目と同様、第5問の出題形式は変わりません。第5問の配点が1番高いので、第5問の出来が合格を左右するといっても過言ではありません。
各設問ごとの得点目標
所感ですが、各設問ごとの理想的な得点配分は下記の通りです。
| 設問 | 配点 | 目標得点 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 20 | 4 | 20% |
| 第2問 | 10~14 | 4 | 約30% |
| 第3問 | 12~18 | 10 | 約80% |
| 第4問 | 16~20 | 14 | 約80% |
| 第5問 | 34~40 | 40 | 約100% |
| 合計 | 100 | 72 | 72% |
第1問
第1問は記述式が出題されますが、捨ててよいです。
第1問で出題される用語は難しく、高得点を目指そうとすると、文言の細かい定義や背景などを細かく暗記しなければなりません。もっとも、原価計算は「暗記」より「計算」を重視すべき科目である以上、細かい事柄まで用語まで暗記するのは「コスパ」が悪いです。
第1問で点を取れなくても、合格できるような学習スタイルを取り入れましょう。
第2問
第2問は空欄補充問題が出題されますが、基本的に捨ててよいです。
原価計算に関する総論的な内容が問われることが多いですが、正直難易度は高いです。高得点を取ろうとすると細かい暗記が必要になるので、他の問題で点数を稼ぐようにしましょう。
多肢選択式の問題が出題された時は、前後の文章から推察して選択肢を絞ることが出来ます。また、2肢選択式の問題が出題された時は、「A」か「B」の2択から選択できます。どちらの出題形式でも、ある程度ヤマ勘で正解することも出来るため、第2問で「30%」正解することは、そこまで難しくありません。
第3問・第4問
出題範囲は定まっていませんが、第3問・第4問ではそこまで複雑ではない原価計算問題が出題されます。
第1問や第2問と比較すると、第3問・第4問は難易度が低めなので、できれば満点を目指してください。配点の高い問題も出題されているので、ゆっくり時間をかけて丁寧に解答しましょう。
第5問
第5問では、決まって原価報告書の作成問題が出題されます。
毎年、ほぼ決まった計算方法が問われるので、そこまで難易度も高くないです。
- 各工事の材料費・労務費・外注費・経費 を問う。
- 未成工事支出金を問う。
- 差異(価格差異、予算差異、操業度差異など)を問う。
他の2科目と同様、第5問で満点を取りたいです。
また、第5問は、1つ間違えると連鎖的に他の問題も間違えてしまう出題形式なので、とにかくミスに注意する必要があります。
毎年出題範囲が決まっていて難易度がそこまで高くないにもかかわらず、配点がかなり高いので、第5問で満点を取れると、かなり合格に近づきます!
まとめ:各設問別対策方法
以上まとめると、私が考える、優先して得点すべき設問は、以下の通りの順番になります。
要は、後半の問題を重視しましょう。
おすすめの勉強法:「アウトプット」を重視しましょう
原価計算に関しては、とにかくアウトプットを重視した学習をしておきましょう。
なぜなら、原価計算は計算がメインで、「個別原価計算」や「総合原価計算」の計算方法を覚えただけでは得点に結びつかないからです。実際に問題を解き、各原価計算方法に慣れるのが一番効率が良いです。
インプットは簡単で良いので、問題集や過去問などを早い段階で解いて、内容を理解しましょう。
補足:おススメのテキスト・予備校・電卓
補足として、おすすめのテキスト・予備校・電卓を簡単に紹介しておきます。
おすすめテキスト
私がおススメするテキストは以下の3冊です。
スッキリわかる 建設業経理士1級 原価計算 第3版 (スッキリわかるシリーズ)
インプット用の基本テキストでは、定番ですが、このテキストがおススメです。
スッキリとける問題集 建設業経理士1級 原価計算 第4版 (スッキリわかるシリーズ)
問題集が欲しい方は、このテキストほぼ1択でしょう。
合格するための過去問題集 建設業経理士1級 原価計算 第5版 (よくわかる簿記シリーズ)
過去問題集が欲しい場合は、このテキストほぼ1択でしょう。
※他のテキストのレビュー記事は↓
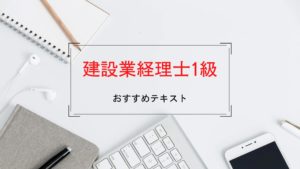
おすすめ予備校
おススメは、「Net-school」の講座です。
※その他の予備校講座の比較記事は↓
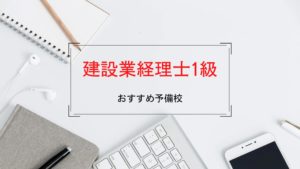
おすすめ電卓
おススメは、CASIOの「JS-20WK」です。
カラーは4色から選べます。(個人的には「ゴールド」が好きです。)
※その他の電卓比較記事は↓
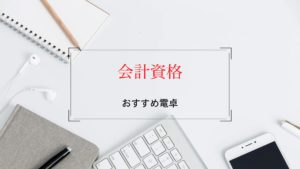
まとめ:「暗記問題」は捨てる。「計算問題」で間違えない。
はい、いかがでしたでしょうか。
何度も語っておりますが、原価計算合格のために一番大事なのは「第5問」で満点を取ることです。(間違えても数点程度に抑えるべきです。)
第5問に関してはほぼ過去問と同様の出題形式なので、過去問を解いて確実に解けるようにしておきましょう。
※1級の他の「財務諸表」「財務分析」に関する対策記事は↓
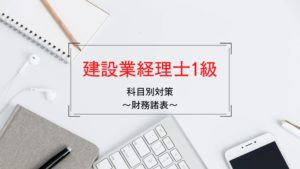
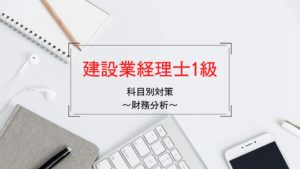
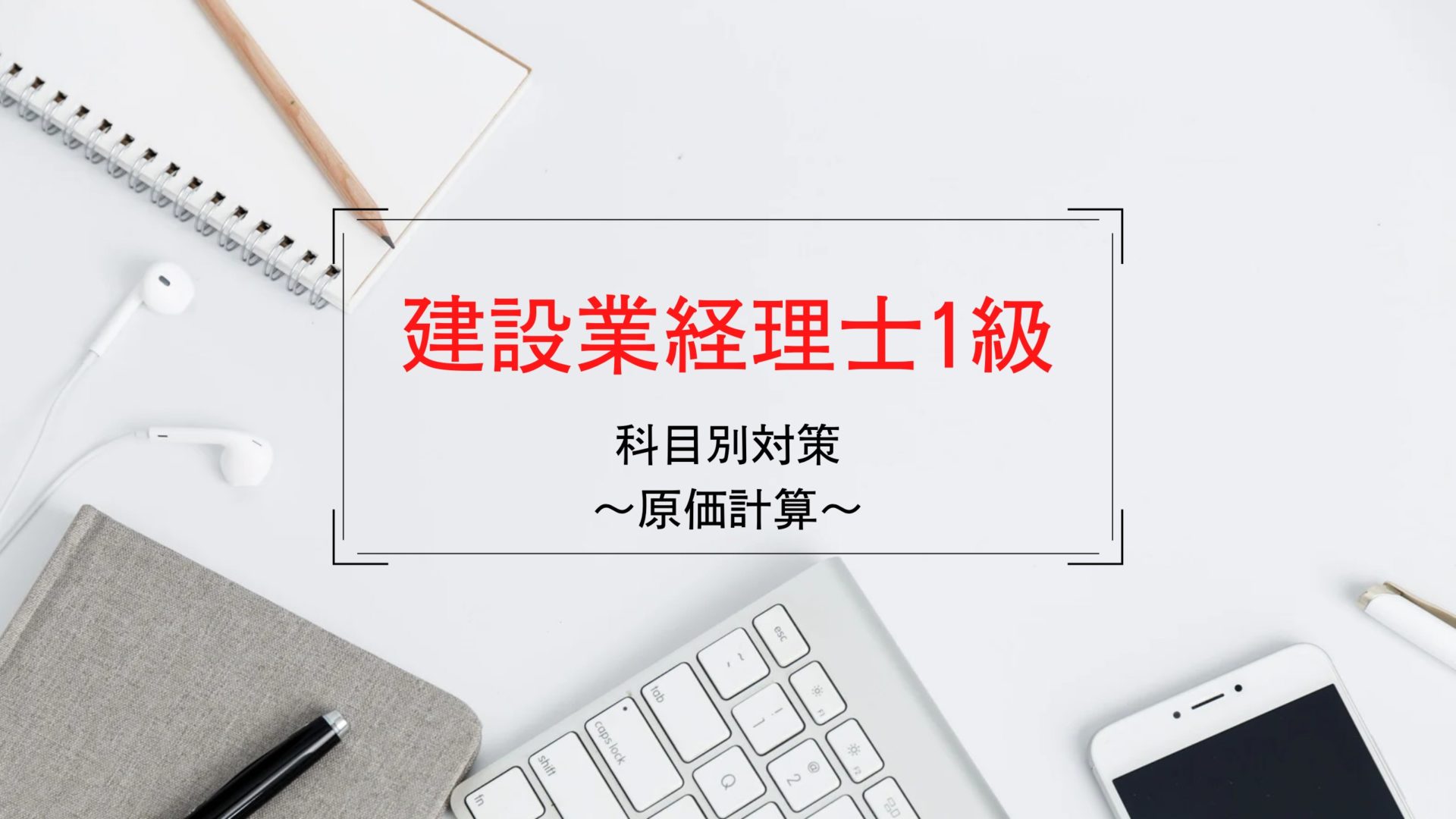




コメント