どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
不動産業界で働いている人や、不動産業界への転職を考えている方は、管理業務主任者試験は取得しておきたいのではないでしょうか。

なお、私は2022年度の管理業務主任者試験に合格できました。
そんな合格者である私の立場から、本記事で、以下の管理業務主任者試験に関する概要をまとめました。
- 試験の概要
- 合格率、難易度、必要な勉強時間
- 試験範囲、出題分野、出題傾向
- 分野別の難易度、得点目標
管理業務主任者試験の合格を目指す方にとって、本記事が少しでも参考になりますと幸いです。
試験の概要
管理業務主任者試験とは、一般社団法人マンション管理業協会が国土交通大臣より指定試験機関の指定を受けて実施する国家試験で、管理業務主任者になるためには合格が必須です。
管理業務主任者とは、マンション管理業者が管理組合等に対して管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務の報告などを行う際に必要な国家資格者をいいます。
試験の概要は、以下のとおりです。
- 試験日:毎年12月1週の日曜日
- 試験地:8地点(北海道・宮城県・東京都・愛知県・大阪府・広島県・福岡県・沖縄県)
- 合格発表日 : 翌年1月中旬ごろ
- 受験手数料 :8,900円 (非課税)
- 事務手数料 :275円 (税込)
合格率(受験者数・合格者数)
過去12年の受験者数・合格者数・合格率・合格基準点をまとめました。
| 実施年度 | 受験者数(人) | 合格者数(人) | 合格率(%) | 合格基準点(点) |
|---|---|---|---|---|
| 平成24年度 | 19,460 | 4,254 | 21.9 | 37 |
| 平成25年度 | 18,852 | 4,241 | 22.5 | 32 |
| 平成26年度 | 17,444 | 3,671 | 21.0 | 35 |
| 平成27年度 | 17,021 | 4,053 | 23.8 | 34 |
| 平成28年度 | 16,952 | 3,816 | 22.5 | 35 |
| 平成29年度 | 16,950 | 3,679 | 21.7 | 36 |
| 平成30年度 | 16,249 | 3,531 | 21.7 | 33 |
| 令和元年度 | 15,591 | 3,617 | 23.2 | 34 |
| 令和2年度 | 15,667 | 3,473 | 23.9 | 37 |
| 令和3年度 | 16,538 | 3,203 | 19.4 | 35 |
| 令和4年度 | 16,217 | 3,065 | 18.9 | 36 |
| 令和5年度 | 14,652 | 3,208 | 21.9 | 35 |


コロナの影響もあり、令和3年度は一時的に受験者数が増加しましたが、受験者は減少傾向にあります。
今後は、受験者数は15,000人程度で推移するものと予測されます。
合格率は、令和3年、令和4年度試験の合格率は10%台となっていますが、平均で21〜24%台を推移しています。
合格基準点は、50点中32点~37点の間で推移しています。
難易度
管理業務主任者試験の直近5年分の合格率について、他の不動産系資格の「宅建試験」「マンション管理士試験」「賃貸不動産経営管理士試験」の合格率と比較しました。
| 合格率 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理業務主任者試験 | 23.2% | 23.9% | 19.4% | 18.9% | 21.9% |
| 賃貸不動産経営管理士試験 | 36.8% | 29.8% | 31.5% | 27.7% | 28.2% |
| 宅建 | 17.0% | 16.8% | 17.7% | 17.0% | 17.2% |
| マンション管理士試験 | 8.2% | 8.6% | 9.9% | 11.5% | 10.1% |


単純に合格率から考えると、各試験の難易度は以下の通りとなります。
合格に必要な勉強時間
一般的に、管理業務主任者試験に合格するために300時間~500時間の勉強時間が必要とされています。ただ、これはあくまでも全くの初学者の場合です。
管理業務主任者試験の受験者は、宅建や賃貸不動産経営管理士などの不動産資格の勉強経験がある方または合格者がほとんどです。勉強経験がある場合、民法や建築基準法の分野で事前知識は一定程度有していますので、100時間程度の勉強で合格することも可能です。



私は、2021年度に宅建と管理業務主任者試験の2つを受験しました。10月の宅建試験の後に、管理業務主任者試験の勉強を始め、勉強時間は約100時間しか確保できませんでしたが、合格レベルに達することが出来ました。
試験範囲・出題分野
試験範囲は、大きく以下の3つの分野に区分できます。
- 法令系
- 管理実務系
- 建築・設備系
過去問5年分の出題内訳について、分野別にまとめました。
| 出題分野 | 出題内訳 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法令系 | 民法など | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 区分所有法など | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
| 標準管理規約 (※区分所有法との複合問題含む) | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | |
| マンション管理適正化法 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| その他法令 | 6 | 9 | 7 | 8 | 4 | |
| 管理実務系 | 標準管理委託契約書 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 会計・簿記 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 建築・設備系 | 建築基準法・消防法など | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 建築物・建築設備など | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| 長期修繕計画ガイドライン | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| 合計 | 50問 | 50問 | 50問 | 50問 | 50問 |
法令系からは約31〜34問、管理実務系からは約6〜7問、建築・設備系からは約10〜12問出題されます。



「法令系」、「管理実務系」、「建物・設備系」の区分についてはサイトにより解釈が若干異なりますので、ご注意ください。
上記の出題分野のうち、難易度が高い問題には黄色マーク、難易度が低い問題には赤色マークを付しました。難易度の低い問題は、確実に正解できるようにするのがポイントです。
なお、参考までに、管理業務主任者試験の公式の試験範囲を掲載しておきます。
| マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第64条で規定されている項目 | 想定される管理業務主任者試験の内容 |
|---|---|
| 1.管理事務の委託契約に関すること | 民法(「契約」及び契約の特別な類型としての「委託契約」を締結する観点から必要なもの)、マンション標準管理委託契約書等 |
| 2.管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること | 簿記、財務諸表論 等 |
| 3.建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること | 建築物の構造及び概要、建築物に使用されている主な材料の概要、建築物の部位の名称等、建築設備の概要、建築物の維持保全に関する知識及びその関係法令(建築基準法、水道法等)、建築物の劣化、修繕工事の内容及びその実施の手続きに関する事項等 |
| 4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること | マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化指針 等 |
| 5.上記1.から4.に掲げるもののほか管理事務の実施に関すること | 建物の区分所有等に関する法律(管理規約、集会に関すること等管理事務の実施を行うにつき必要なもの)等 |
各設問の難易度・得点目標
各設問の難易度について、詳細に解説します。
難易度高:「民法等」、「建築物・建築設備等」 ⇨ 6割取れるように。
試験範囲の中で、「民法等」・「建築物・建築設備等」の分野の問題は難易度が高いものが多いです。
民法では、難易度の高い問題が出題されます。条文数は全部で1000程度あり、ヤマを張るのも難しいので、全体を満遍なく勉強しましょう。
建築物・建築設備等の分野は、基本テキストに掲載されていない範囲から出題されることがあるので、高得点を目指す場合はかなり細かい範囲まで学習しなければなりません。捨て問は捨てて、過去問類似の問題は確実に解答できるようにするのがポイントです。



難易度の高い分野の問題は、6割程度を目指しましょう。
難易度低:「会計・簿記」「マンション管理適正化法」 ⇨ 満点を目指したい。
「会計・簿記」、「マンション管理適正化法」の分野の問題は比較的難易度が低いため、得点源にしておきたいです。
会計・簿記では、仕訳問題が毎年2〜3問出題されますが、基本的な事項を押さえておければ確実に正解できる問題で、いわばサービス問題といってもよいです。出題形式も過去問とほぼ同じなので、過去問対策をしっかり行っておきましょう。
マンション管理適正化法の分野からは、毎年5問(第46〜第50問)が確実に出題されます。基本的に管理業務主任者の選任業務・収納管理口座に関する問題がメインですが、覚える事項も少なく、問題の難易度も高くないので、確実に特典できるようにしておきましょう。



難易度の低い分野の問題は、できれば満点を目指しましょう!
まとめ:分野ごとの難易度を把握して、メリハリをつけて学習しよう。
管理業務主任者試験の概要について説明しましたが、いかがでしたでしょうか。
管理業務主任者試験は、分野ごとの問題の難易度に大きく開きがある点が特徴です。分野ごとの問題の難易度を把握して、あらかじめ目標点を設定した上で、メリハリをつけた学習を心がけましょう。
なお、使用するテキストや予備校が決まっていない方は、以下の記事も併せてご覧ください。
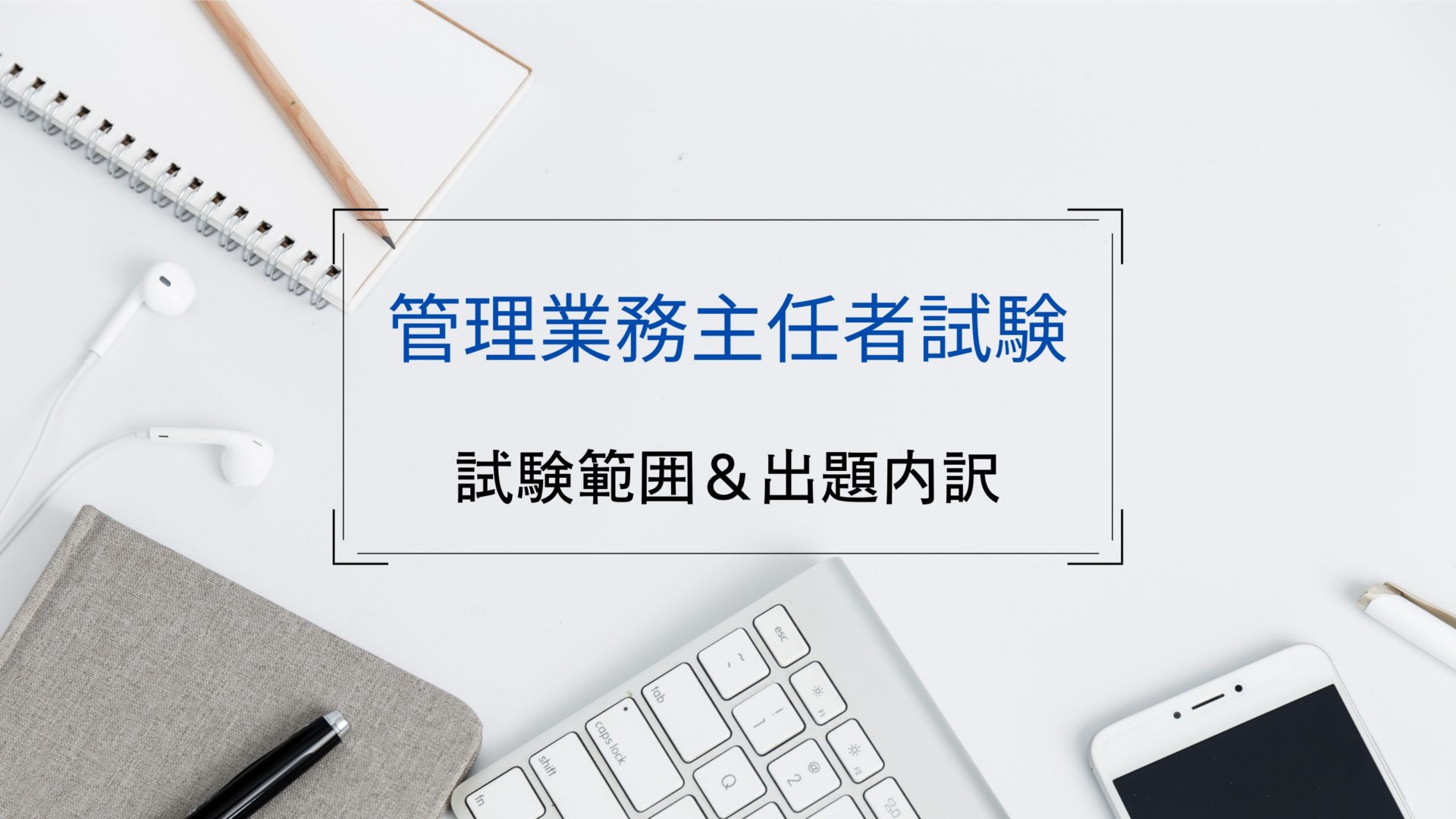
コメント