どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
初めて行政書士試験を受験する方は、まずは、行政書士試験とはどういうものなのか、理解しておく必要があります。
そこで、本記事にて、行政書士試験の概要をまとめました。これから行政書士試験を受験される方の参考になりますと幸いです。
試験の概要
試験日程・試験時間など
行政書士試験の試験の概要は、以下の通りです。
- 試験日:毎年11月第2週の日曜日
- 試験時間:13:00〜16:00(3時間)
- 試験場所:全47都道府県で実施
- 受験手数料:7000円
- 申込期間:7月下旬から8月下旬ごろ(※インターネット申込も可)
特筆すべきは、試験時間の長さです。他の試験は2時間前後のものが多いですが、行政書士試験の場合は3時間です。また、問題も記述式含む60問あるため、時間に余裕がありません。
3時間の長時間に耐えるだけの集中力が必要とされます。
受験者・合格率・難易度
行政書士試験の過去10年分の受験者数・合格者数・合格率は、以下の通りです。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 47,850人 | 5,802人 | 12.1% |
| 令和3年度 | 47,870人 | 5,353人 | 11.2% |
| 令和2年度 | 41,681人 | 4,470人 | 10.7% |
| 令和元年度 | 39,821人 | 4,571人 | 11.5% |
| 平成30年度 | 39,105人 | 4,968人 | 12.7% |
| 平成29年度 | 40,449人 | 6,360人 | 15.7% |
| 平成28年度 | 41,053人 | 4,084人 | 10.0% |
| 平成27年度 | 44,366人 | 5,820人 | 13.1% |
| 平成26年度 | 48,869人 | 4,043人 | 8.3% |
| 平成25年度 | 55,436人 | 5,597人 | 10.1% |
受験者について、過去10年で一番受験者数が多かった年が平成25年度(2013年)で、受験者数が「55,436人」でした。一番受験者数が少なかった年が平成30年度(2018年)の「39,105人」です。一時期は、受験者はピーク時の約60%に落ち込みました。
令和3年度は、コロナの影響もあってか、受験者が増えていますが、それでもピーク時には達していません。来年以降の傾向も読めませんが、少なくとも約40000人程度を推移するのではないでしょうか。
合格率について、約8%〜16%の間で推移していますが、平均では約11%です。なお、受験者数が減っている影響もあってか、合格率は近年上昇傾向にあります。
難易度について、行政書士試験の受験者が6万人以上いた頃と比較すると、難易度は低くなっていますが、いまだ9人に1人しか受からない試験なので、難易度の高い試験と言えます。
試験範囲
試験範囲は、大まかに分けて法令科目と一般知識科目の2つに分けられます。
- 法令科目:法令基礎・憲法・行政法・民法・商法
- 一般知識:政治/経済/社会・情報通信/個人情報保護・文章理解
出題形式
出題形式及び各配点は以下の通りです。
- 5肢選択式 … 5つの選択肢の中から正しいものを回答する形式(1問4点)
- 多肢選択式 … 複数の選択肢の中から正しいものを回答する形式 (1問8点:計4解答)
- 記述式 … 記述(40字)による形式 (1問20点)
行政書士試験において、多くの受験生が苦戦するのが「記述式」です。普段から記述式に対応できるような勉強方法を取り入れましょう。
合格点
行政書士試験は、全300点中180点(全体の60%)が合格点となっています。この180点は絶対基準なので、試験の難易度によって変わりません。試験の難易度により平均点が増減する場合も考えられますが、180点獲得すれば合格となります。
全体の300点が占める配点は以下の通りです。
- 法令科目:244点(合計46問)
- 一般知識:56点(合計14問)
得点配分
300点の内訳を、試験範囲・出題形式・配点ごとに分類したものが、以下の表になります。
| 大区分 | 小区分 | 問題番号 | 出題形式 | 問題数 | 配点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法令等 | 基礎法学 | 問題1.2 | 5肢択一式 | 2問 | 8点 |
| 憲法 | 問題3~7 | 5肢択一式 | 5問 | 20点 | |
| 問題41 | 多肢選択式 | 1問 | 8点 | ||
| 行政法 | 問題8~26 | 5肢択一式 | 19問 | 76点 | |
| 問題42.43 | 多肢選択式 | 2問 | 16点 | ||
| 問題44 | 記述式 | 1問 | 20点 | ||
| 民法 | 問題27~35 | 5肢択一式 | 9問 | 36点 | |
| 問題45.46 | 記述式 | 2問 | 40点 | ||
| 商法・会社法 | 問題36~40 | 5肢択一式 | 5問 | 20点 | |
| 一般知識 | 問題47〜60 | 5肢択一式 | 14問 | 56点 | |
| 合計300点 |
学習のポイント
以上を踏まえた、行政試験の学習におけるポイントは次の3点です。
①本番の時間配分に注意する。
試験時間が3時間と長いものの、問題数が60問(※記述式含む)と多いため、うっかりしていると、時間切れとなってしまう恐れがあります。
試験が始まったら、どの問題から解いていくか、各問題にどのくらい時間をかけるか、本番の方針を決めておきましょう!
※私がおすすめする試験の回答順番&時間配分について、以下の記事をご参照ください。
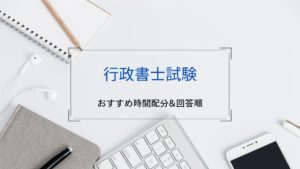
②足切りに注意する。
行政書士試験には、法令科目50%、一般知識約40%という、足切り基準があります。このうち、足切りにかかりやすいのは「一般知識」の方です。
私は一般知識は最低限の学習で良いと考えていますが、足切りにかかってしまっては元も子もないので、得点策略は事前に練っておきましょう。
※私がおすすめする一般知識の足切り対策について、以下の記事をご参照ください。
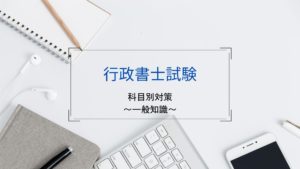
③記述式の対策を怠らない。
行政書士試験では、多肢選択式問題に加え、記述式問題が計3問出題されます。
3問の配点は計60点で、全体の20%を占めています。とすると、記述式を捨てて合格するのは難しいです。
日頃から記述式対策用の学習にも取り組んでおきましょう。
※私がおすすめする記述式対策について、以下の記事をご参照ください。
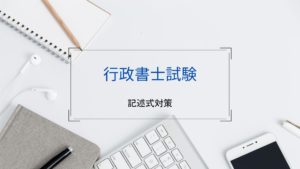
各科目の勉強方法
行政書士試験の試験範囲は広いので、各科目ごとに対策方法が異なります。おすすめの科目別の勉強方法については、「法令科目」と「一般知識」に分けて、別記事にて紹介しております。こちらをご参照ください。
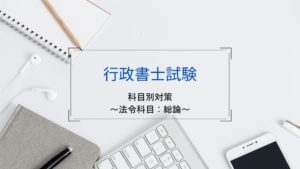
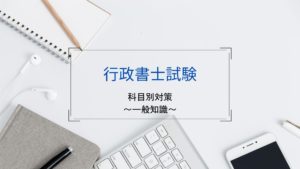
合格体験記
幸いにも、私は2020(令和2年度)年に行政書士試験に合格することが出来ました。合格体験記を別記事にて公開しておりますので、興味のある方はぜひご覧ください。
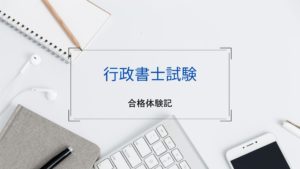
まとめ:行政書士試験の概要を知った上で試験対策を始めよう。
はい、いかがでしたでしょうか。
行政書士試験は試験範囲が広く、難易度の高い試験なので、ある程度のまとまった勉強時間が必要になります。
行政書士試験の特徴を踏まえた上で、科目別に勉強を始めましょう。
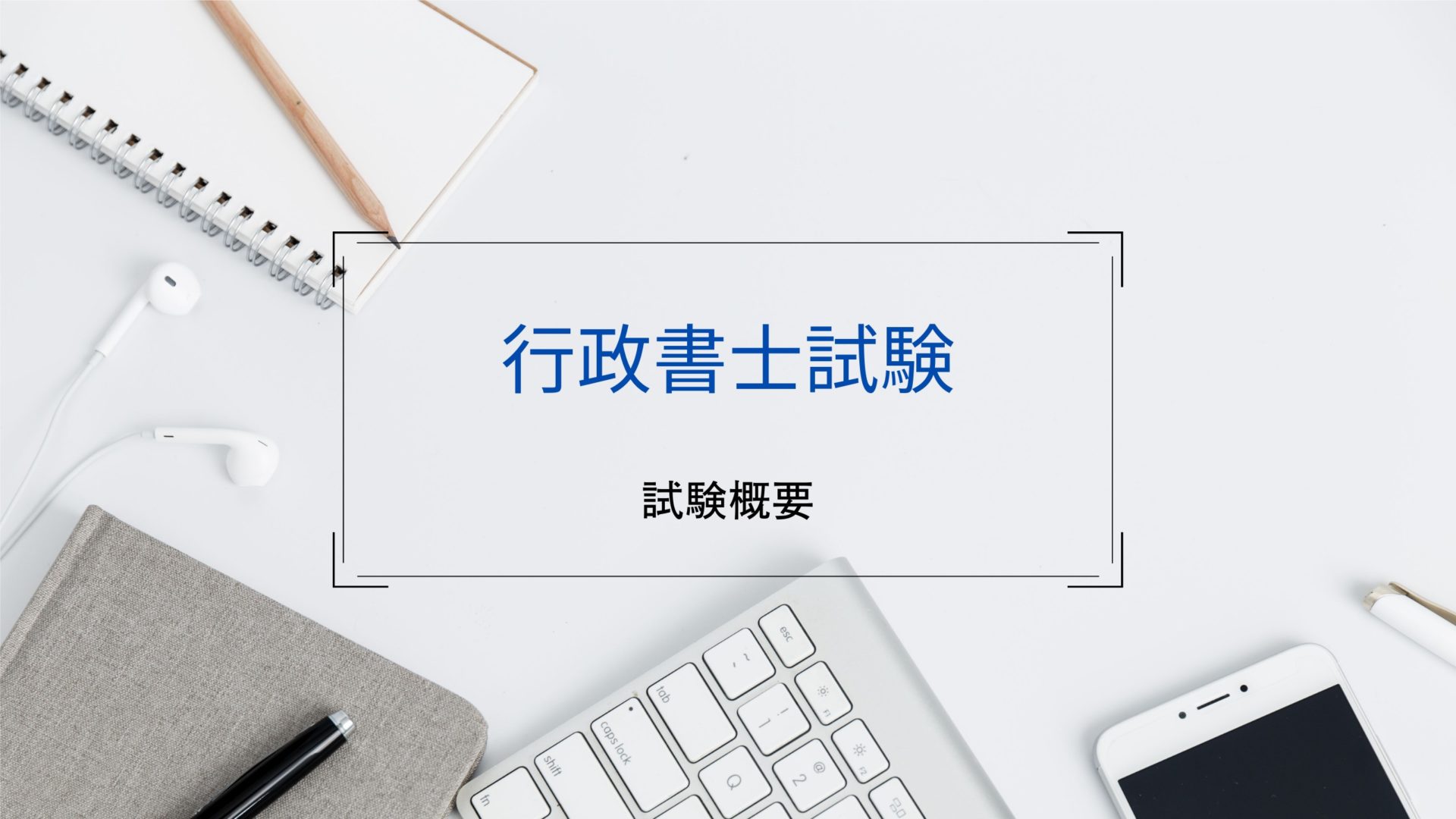
コメント