どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
行政法のうち、「行政不服審査法」は毎年必ず3問出題されます。難易度がそこまで高くないので、できれば満点を取りたいところです。
もっとも、行政不服審査法は手続きの話が多く、初見では理解が難しいので、行政不服審査法に苦手意識を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
私は、2020年度の行政書士試験に独学にて一発合格することができました。
そんな合格者の私が、本記事にて行政不服審査法の学習のポイントを解説します。行政不服審査法を勉強する上での参考になりますと幸いです。
行政不服審査法の全体像の確認
法律の冒頭部分には目次があります。全体像を理解するのにちょうど良いですので、まずは、目次を見て行政不服審査法の全体像を確認しましょう。
第一章 総則(第一条 ― 第八条)
e=gov 法令検索
第二章 審査請求
第一節 審査庁及び審理関係人(第九条 ― 第十七条)
第二節 審査請求の手続(第十八条 ― 第二十七条)
第三節 審理手続(第二十八条 ― 第四十二条)
第四節 行政不服審査会等への諮問(第四十三条)
第五節 裁決(第四十四条 ― 第五十三条)
第三章 再調査の請求(第五十四条 ― 第六十一条)
第四章 再審査請求(第六十二条 ― 第六十六条)
第五章 行政不服審査会等
第一節 行政不服審査会
第一款 設置及び組織(第六十七条 ― 第七十三条)
第二款 審査会の調査審議の手続(第七十四条 ―第 七十九条)
第三款 雑則(第八十条)
第二節 地方公共団体に置かれる機関(第八十一条)
第六章 補則(第八十二条 ― 第八十七条)
附則
行政不服審査法は、全部で6つの章に分かれています。
最後の第6章「補足」を除くと、「1総則」「2審査請求」「3再調査の請求」「4再審査請求」「5行政不服審査法」の5つの章に分けられますが、試験対策の観点から重要な条文は、「2審査請求」「3再調査の請求」「4再審査請求」の章にある条文です。
行政不服審査法では、「審査請求」と「再調査請求」と「再審査請求」の3つの請求について詳細に規定されているので、この3つの請求の類似点・相違点を押さえましょう。
また、「1総則」の章の中に、これら3つの請求の定義が規定されていますので、まずは、「1総則」の章に記載の条文を理解しておきましょう。
ポイント①:「審査請求」「再調査請求」「再審査請求」を区別して理解。
「1総則」の章の中の、3つの請求の定義を定めた条文について、詳細に解説します。
(目的等)
第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。
2 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下単に「処分」という。)に関する不服申立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。(処分についての審査請求)
第二条 行政庁の処分に不服がある者は、第四条及び第五条第二項の定めるところにより、審査請求をすることができる。(不作為についての審査請求)
第三条 法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいう。以下同じ。)がある場合には、次条の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。(審査請求をすべき行政庁)
第四条 審査請求は、法律(条例に基づく処分については、条例)に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。一 処分庁等(処分をした行政庁(以下「処分庁」という。)又は不作為に係る行政庁(以下「不作為庁」という。)をいう。以下同じ。)に上級行政庁がない場合又は処分庁等が主任の大臣若しくは宮内庁長官若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する庁の長である場合 当該処分庁等
二 宮内庁長官又は内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項に規定する庁の長が処分庁等の上級行政庁である場合 宮内庁長官又は当該庁の長
三 主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合(前二号に掲げる場合を除く。) 当該主任の大臣
四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該処分庁等の最上級行政庁(再調査の請求)
第五条 行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について第二条の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。2 前項本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 当該処分につき再調査の請求をした日(第六十一条において読み替えて準用する第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日)の翌日から起算して三月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき決定をしない場合
二 その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合(再審査請求)
第六条 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。2 再審査請求は、原裁決(再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決をいう。以下同じ。)又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
暗記までは不要ですが、上記の条文を読んで、「審査請求」「再調査請求」「再審査請求」とは何か?、各請求の要件は何か?誰が請求できるか?を理解してください。(特に大事と判断した条文には赤字を付けました。)
審査請求できる場合(2条・3条)
審査請求ができる要件は、①行政庁の処分に不服がある場合(2条)、または②行政庁に不作為がある場合(3条)です。
審査請求人は、①の場合「不服がある者」(2条)、②の場合は「処分についての申請をした者」(3条)となります。
再調査請求できる場合(5条)
再調査請求ができる要件は、「行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合」(4条1項以外の場合)において、「法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるとき」です。(※不作為は含まれません。)
審査請求人は、「当該処分に不服がある者」です。
再審査請求できる場合(6条)
再審査請求ができる要件は、「行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合」です。(※不作為は含まれません。)
審査請求人は、「審査請求の裁決に不服がある者」です。
ポイント②:「請求期間」「審理手続」「執行停止」「採決」を理解。
3つの請求の要件・審査請求人を押さえた上で、各請求の「請求期間」・「審理手続」「執行停止」「採決」を覚えましょう。
請求期間(18条・54条・62条)
まず、各請求の審査請求期間を条文丸ごと暗記してください。
まずは審査請求から。
(審査請求期間)
第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 略
e-Gov法令検索
次に、再調査請求です。
(再調査の請求期間)
第五十四条 再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
そして、再審査請求です。
(再審査請求期間)
第六十二条 再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
大事なのは期間(1か月or3か月or1年)と開始起算日(処分(決定)を知った日or 処分(決定)があった日の翌日から)です。例外が「正当な理由があるとき」です。
違いを正しく整理しておきましょう。
審理手続(28~42条・61条・66条)
該当条文が多いので引用しませんが、大事なのは、「主語」の部分です。主に「審理員」「行政庁等」「審査請求人」「参加人」が出てくるので押さえておきましょう。
主語は「審理員」が多いので、「行政庁等」「審査請求人」「参加人」が主語になっている条文が問われることが多いです。(ex)「弁明書」「反論書」「意見書」を提出するのはそれぞれ誰か など。)審理員以外が主語となる条文を理解しておきましょう。
執行停止(25条・61条・66条)
審査請求の場合の執行停止に関して規定した条文が25条です。
(執行停止)
第二十五条 審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる。
3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
4 前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
5 審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
6 第二項から第四項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
7 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。
25条は第1項〜第7項まで全て大事ですので、必ず理解できるようになりましょう。覚え方は、以下の通りになります。
補足で、第6項・7項も暗記しておきましょう。
なお、再調査の請求の場合は、第61条にて第25条(第3項を除く。)を準用するという形式をとってます。
(審査請求に関する規定の準用)
第六十一条 第九条第四項、第十条から第十六条まで、第十八条第三項、第十九条(第三項並びに第五項第一号及び第二号を除く。)、第二十条、第二十三条、第二十四条、第二十五条(第三項を除く。)、第二十六条、第二十七条、第三十一条(第五項を除く。)、第三十二条(第二項を除く。)、第三十九条、第五十一条及び第五十三条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第25条第3項は準用されないので、注意が必要です。
また、再審査請求の場合も、第66条にて第25条第2項を準用しています。
(審査請求に関する規定の準用)
第六十六条 第二章(第九条第三項、第十八条(第三項を除く。)、第十九条第三項並びに第五項第一号及び第二号、第二十二条、第二十五条第二項、第二十九条(第一項を除く。)、第三十条第一項、第四十一条第二項第一号イ及びロ、第四節、第四十五条から第四十九条まで並びに第五十条第三項を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。2 再審査庁が前項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である場合には、前項において準用する第十七条、第四十条、第四十二条及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
第25条第2項のみ(申立or職権で執行停止できる)のみ準用されている点に注意が必要です。
裁決(45,46条,49条・58条,59条・64,65条)
以下、採決に関して定めた条文7つを引用します。
・処分
(処分についての審査請求の却下又は棄却)
第四十五条 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
2 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
3 審査請求に係る処分が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法又は不当であることを宣言しなければならない。(処分についての審査請求の認容)
第四十六条 処分(事実上の行為を除く。以下この条及び第四十八条において同じ。)についての審査請求が理由がある場合(前条第三項の規定の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。2 前項の規定により法令に基づく申請を却下し、又は棄却する処分の全部又は一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一 処分庁の上級行政庁である審査庁 当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二 処分庁である審査庁 当該処分をすること。3 前項に規定する一定の処分に関し、第四十三条第一項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。
4 前項に規定する定めがある場合のほか、第二項に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が同項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。
(不作為についての審査請求の裁決)
第四十九条 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。2 不作為についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
3 不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
一 不作為庁の上級行政庁である審査庁 当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。
二 不作為庁である審査庁 当該処分をすること。4 審査請求に係る不作為に係る処分に関し、第四十三条第一項第一号に規定する議を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めに係る審議会等の議を経ることができる。
5 前項に規定する定めがある場合のほか、審査請求に係る不作為に係る処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施その他の手続をとるべき旨の定めがある場合において、審査庁が第三項各号に定める措置をとるために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続をとることができる。
・再調査
(再調査の請求の却下又は棄却の決定)
第五十八条 再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。2 再調査の請求が理由がない場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。
(再調査の請求の認容の決定)
第五十九条 処分(事実上の行為を除く。)についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。2 事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更する。
3 処分庁は、前二項の場合において、再調査の請求人の不利益に当該処分又は当該事実上の行為を変更することはできない。
・再審査請求
(再審査請求の却下又は棄却の裁決)
第六十四条 再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する。2 再審査請求が理由がない場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
3 再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
4 前項に規定する場合のほか、再審査請求に係る原裁決等が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、再審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、原裁決等を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却することができる。この場合には、再審査庁は、裁決の主文で、当該原裁決等が違法又は不当であることを宣言しなければならない。
(再審査請求の認容の裁決)
第六十五条 原裁決等(事実上の行為を除く。)についての再審査請求が理由がある場合(前条第三項に規定する場合及び同条第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、再審査庁は、裁決で、当該原裁決等の全部又は一部を取り消す。2 事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合(前条第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁に対し、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃すべき旨を命ずる。
上記7つの条文の内容は似ています。
「処分」「不作為」「事実上の行為」「原裁決」に対する「却下」「棄却」「認容(取消・変更)」の「判決」「決定」のいずれかの組み合わせとなります。
3つの請求毎に、どのような裁決が下されるのかを区別して暗記するようにしましょう。
まとめ:3つの請求の類似点・相違点を意識しつつ学習しましょう。
はい、行政不服審査法のポイントをまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか。
審査請求・再調査請求・最審査請求の内容と類似点・相違点、また3つの請求ごとの4つのポイントを理解した上で、本記事で解説しきれなかった周辺知識(行政不服審査会、判決の拘束力 など)を学習できれば、合格に十分な知識が身につきます。
条文をベースに、内容を理解してみましょう。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければ、他の行政法の「5分で解説シリーズ」もご覧ください。
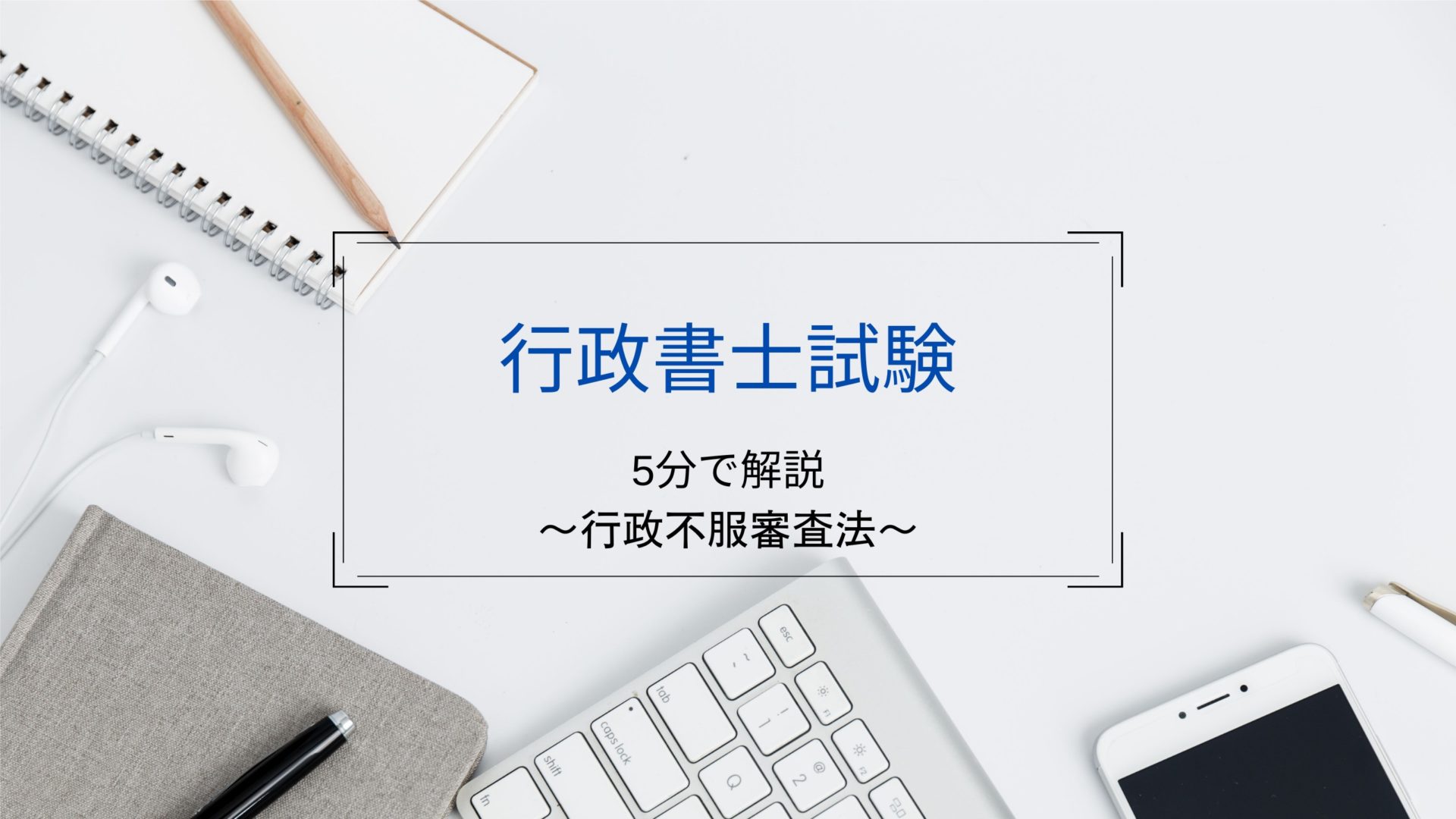
コメント