どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
宅建の合格率は、約15%〜約17%です。6人に1人しか合格しないので、人によっては何度も不合格になってしまう場合もある、比較的難易度の高い試験です。
しかし、私は幸いにも、2021年度10月の宅建試験に独学で1発合格することが出来ました。
そんな私が、合格までにかかった勉強時間・勉強内容などを、本記事で合格体験記として掲載します。合格を目指す皆さんにとって、少しでも参考になりますと幸いです。
結論:合格までの勉強時間は「150時間」
結論から言うと、私は150時間の勉強時間で合格できました。
- 勉強開始時期:試験の約2ヶ月前(8月23日〜)
- 1週間の勉強時間:約20時間
- 勉強時間:約150時間
宅建の試験範囲には民法が含まれていますが、行政書士試験の試験範囲にも民法が含まれていたこともあり、民法の勉強はほぼ不要でした。借地借家法の細かい規定を暗記したくらいの勉強しかしておりません。
1週間の勉強時間
私の1週間の勉強時間は、約20時間です。
- 平日:約2時間
- 休日:約4時間
私は会社員で、日中は働いていたので、勉強は仕事前か仕事後にしかできません。なんとか勉強時間を捻出して平日は2時間程度、休日は4時間程度は勉強していました。(私の場合はブログやYoutubeなどもやっているので、これ以上は時間が取れません。)
勉強内容(時系列ベース)
私の勉強内容や勉強方法について、時系列ベースで紹介します。
8月下旬~:勉強開始
宅建試験の申し込みは例年7月1日より始まります。試験に申し込んだのは7月1日でしたが、本格的に勉強を開始したのは、試験の約2ヶ月前の8月23日でした。
私は8月22日(日)にTOEIC試験を控えており、それまではTOEICの勉強に専念していました。TOEICの受験が終わるとすぐに宅建試験の勉強を始めました。試験まで2ヶ月しかないので、勉強開始時点で既に余裕がありませんでした。
使用テキスト:合格のトリセツ
私が使っていたテキストは「宅建 合格のトリセツ」というテキストです。
本テキストを選んだ理由として、本テキストは電子版が出版されていたからです。宅建のテキストはどれも分厚く、持ち運びに苦労するのですが、電子版だと持ち運びに困りません。携帯性を重視して、電子版のテキストを選びました。
合格に必要な知識が詰まっており、また内容もコンパクトにまとまっていたため、合格できたので本テキストのおかげといっても過言ではないです。テキスト選びに悩んだ場合は、是非みなさんもこのテキストを使ってみて下さい!
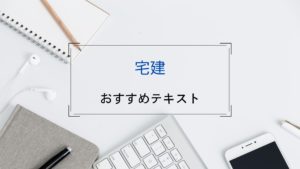
~9月2週:一通りのインプットを終了。
試験まで時間がなく、過去問演習等の時間も十分に確保したかったことから、とにかく早めにテキストを1周分通読することを目標としていました。
その甲斐もあり、勉強を開始してから3週間後の9月2週目には、テキストを通読できました。
スピード重視だったので、この時点でテキストの内容を全て理解できていたわけではありません。「全体像を理解する」という程度の理解レベルでした。細かい知識は、過去問演習をしながら理解できれば良い、と思っていました。(合格できたので、結果的にはこの勉強方法で間違ってなかったと思います。)
~9月4週:過去問演習メインに学習する。
インプットが終わって以降は、過去問対策に切り替えました。
私の場合は、ひとまず過去問を直近3回分(2020年度10月試験・2020年度12月試験・2019年度)解きました。過去問を解くにあたっては、試験本番と同様のタイムスケジュールで解きました。全問解き終えた後、解説もきちんと確認しました。
私の場合、「法令分野」や「宅建業法」は比較的得点できていたのですが、「法令上の制限」などがあまり得点できていませんでした。建築基準法や都市計画法まできちんと勉強しないと合格できない、と感じたので、苦手分野の学習をメインに取り組みました。
過去問対策に関して
過去問を解くにあたり、私は過去問題集は購入しませんでした。
最近は、過去問が無料で解けて、解説も確認できるサイトもたくさんあるので、必ずしも過去問集の購入は必須ではないように思います。
~10月3週目:ひたすらインプット&アウトプットを繰り返す。
過去問を3回分解き終えて以降は、ひたすらインプット&アウトプットを繰り返しました。
過去問ドットコムを利用して分野別に宅建の問題を解き、分からない部分があればテキストの内容を確認する、という勉強法を本番まで繰り返しました。試験まで時間もわずかなので、かなり本腰が入っていた気がします。
※「賃貸不動産経営管理士試験」の勉強も始めていた。
私は同じ年度の11月に「賃貸不動産経営管理士試験」、12月に「管理業務主任者試験」を受けるつもりでした。いずれの試験も、10月の宅建の勉強を終えてから勉強を始めても間に合わない気がしたので、賃貸不動産経営管理士試験の勉強も、10から並行的に取り組んでいました。
試験日:10月17日
ついに迎えた宅建試験本番、今までやってきたことを信じて会場に向かいました。
自己採点の結果は、36/50点でした・・・。
昨年度の10月試験の合格点は38/50点だったので、正直落ちたと思いました。「合格ボーダー下がってくれ!」とひたすら願ってました。
合格発表日:12月1日
合格発表日は試験約1か月半後の12/1(水)9:30~でした。
合格発表ページに訪問して、自分の受験番号を探したところ、合格者番号がありました。自信は全くなかったのですが、合格出来ていて一安心しました。
※合格発表日に合格証が届く
私は都内在住ですが、合格発表からわずか2時間後の11:30頃には、合格証が届きました。実際には、合格発表日以前に既に発送されているようですね。
念のため、合格証を添付しておきます。

なお、合格した場合でも点数は開示されません。点数開示制度はあるようですが、私は利用しませんでした。
必要な勉強時間は、人により異なる。
宅建の勉強時間・勉強内容を振り返りましたが、いかがでしたでしょうか。
私の場合、約150時間の勉強で合格できましたが、民法の知識をある程度持っていたことが理由です。民法が一番難しいので、全くの初学者の場合だと、総勉強時間は約300時間程度は必要になるのではないかと思います。
宅建合格を目指す方にとって、本記事が少しでも参考になりますと幸いです。


コメント