どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
行政法のうち、国家賠償法は、毎年5肢選択式にて毎年2問程度(8点分)出題されます。配点は高くないものの、問題の難易度は低いため、出来れば満点を獲得したい分野です。
ただし、国家賠償法の出題範囲はそれなりに広いため、苦手としている方も多いのではないでしょうか?
私は、2020年度の行政書士試験に独学で一発合格することができました。
そんな私が、本記事で、国家賠償法の学習ポイントや、押さえるべき事項について解説します。国家賠償法の学習方法について悩んでいる方の参考になりますと幸いです。
国家賠償法は、たった6条しかない。
国家賠償法は、条文は全部で6条しかありません。少ないので、条文は全て一度は読んでおきましょう。
第一条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。第二条
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。第三条
前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。第四条
国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。第五条
国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。第六条
e=gov法令検索
この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。
最も重要な条文は、第1条第1項です。
ポイント①:国家賠償法第1条の要件・重要判例を覚えましょう。
国家賠償法は条文が少ないので、判例から出題されることが多いです。中でも、第1条第1項に関する判例が多く出題されます。
そのため、まずは第1条第1項を正確に暗記した上で、要件ごとに整理して判例を学習しましょう。
第1条第1項
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
本条の要件は、以下の5つです。
- 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、
- その職務を行うについて、
- 故意又は過失によって
- 違法に
- 他人に損害を加えたとき
要件のうち、特に①・②・④の3つが重要です。以下、要件ごとに区別して覚えるべき判例を解説していきます。
①:「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員」に関する判例(4つ)
①の要件について、出題可能性の高い重要判例を4つに絞ってまとめました。
| 案件名 | 判旨(一部抜粋) |
|---|---|
| 都道府県警察の交通犯罪捜査事務の帰属主体(S54.7.10) | 都道府県警察の警察官が交通犯罪の捜査を行うにつき 他人に損害を与えた場合は責任を負うのは原則して当該都道府県であり、 国は原則としてその責めを負うものではない。 |
| 社会福祉法人の設置運営する児童養護施設における事故(H19.1.25) | 児童養護施設の長は、本来都道府県が有する公的な権限を委譲されて 都道府県のために事務を行使していると解されるから、 社会福祉法人の設置運営する児童養護施設に入所した児童に対する教育看護行為は、 都道府県の公権力の行使にあたる公務員の職務行為と解される。 |
| 公立学校の学校事故(S62.2.6) | 「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動も含まれる。 |
| X線関節撮影における加害行為者・加害行為の特定(S57.4.1) | 国又は公共団体に属する一人又は数人の公務員による 一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生じさせた場合において、 それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを 特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに 故意又は過失による違法行為があつたのでなければ右の被害が 生ずることはなかつたであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよ、 これによる被害につき専ら国又は当該公共団体が国家賠償法上又は民法上賠償責任を負うべき関係が存在するときは、国又は当該公共団体は、加害行為の不特定をもって損害賠償責任を免れることはできない。 (※関係者すべてが公務員である必要あり。) |
責任を負うのは都道府県か国か?、該当行為が公権力の行使にあたると言えるか?など、責任主体を意識して判例を覚えるようにしましょう。
②「職務を行うについて」に関する判例(1つ)
②要件で理解しておくべき判例は1つあります。いわゆる「職務外形説」を採用したとされるS31.11.30判例です。
本事案は、「巡査である加害者が、職務管轄外の範囲で非番時に制服を着て勤務をして、現金を搾取する目的で、被害者を射撃し、死亡させる」という、なかなかのレアケースです。
本件において、D巡査がもっぱら自己の利をはかる目的で警察官の職務執行をよそおい、被害者に対し不審尋問の上、犯罪の証拠物名義でその所持品を預り、しかも連行の途中、これを不法に領得するため所持の拳銃で、同人を射殺して、その目的をとげた、判示のごとき職権濫用の所為をもって、同条にいわゆる職務執行について違法に他人に損害を加えたときに該当するものと解した(原審の)解釈は正当でであるといわなければならない。
けだし、同条は公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合にかぎらず自己の利をはかる意図をもってする場合でも、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしてこれによって、他人に損害を加えた場合には、国又は公共団体に損害賠償の責を負わしめて、ひろく国民の権益を擁護することをもって、その立法の趣旨とするものと解すべきであるからである。
細かい文言を暗記する必要はないですが、職務外形説は理解してください。
③「違法に」に関連する判例(5つ)
この要件に関しては、具体的なケースを確認しておきましょう。本記事では5つに絞って掲載しました。
| 案件名 | 判旨(一部抜粋) |
|---|---|
| パトカー追跡による第三者の損害 (S61.2.27) | 追跡行為が違法であるというためには、右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、追跡の開始・継続もしくは追跡の方法が不相当であることを有するものと解すべき。 (結論:追跡行為は違法でない。) |
| 所得税更正処分の違法性 (H5.3.11) | 税務署長のする所得税の更正は、所得金額を課題に認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠償法1条1項に言う違法があったとの評価を受けるものではない。税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り、違法の評価を受ける。 (結論:更正処分は違法ではない。=原告が調査に応じなかった落ち度もある。) |
| 健康管理手当等の受給権を取得した被爆者が日本国外に移住地を移した場合に、受給権を失権するとする402号通達解釈誤りの違法性 (H19.11.1) | 402号通達の失権取り扱いの定めは被爆者援護法に反する解釈なので、不支給の取り扱いは法に反しているが、担当者が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くことなく漫然と上記行為をしたと認められるような事情がある場合に限り、違法の評価がなされる。 (結論:402号通達発出前→違法でない 402号通達発出後→違法 解釈が違うことが認識可能だったから。) |
| 裁判官の職務行為の違法性 (S57.3.12) | 裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在していたとしても、これによって当然に違法となるわけではなく、違法といえるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特段の事情があることを必要とすると解するのが相当である。 (結論:違法ではない。) |
| 検察官の公訴提起の違法性 (S53.10.20) | 刑事事件において無税の判決が確定したというだけで直ちに起訴前の逮捕・勾留、公訴の提起・追行、起訴後の勾留が違法となるということはない。 (結論:違法ではない。→有罪の嫌疑があればよい。) |
細かい判旨を暗記する必要はないですが、結論は覚えてください。(違法ではないケースがほとんどです。)
なお、「違法二元説」や「職務行為基準説」といった細かい論点の解説は、本記事では省略します。
※違法性:権限不行使に関する判例(リーディングケース1つ+3つ)
作為(行った行為)だけでなく、不作為(何らの行為も行わなかった)に関する判例も出題されるため、違法性の要件に関連して権限不行使に関する判例も押さえておくことが大事です。
リーディングケースの判例(権限不行使が違法となる場合は?)
権限不行使に関するリーディングケースが「H.1.11.24」判例(宅建業者の監督事例)です。
事案を簡単にまとめると、宅建業法の免許基準を満たしていない(資金に余裕がない)業者に免許を与えたり、免許の更新をした知事の行為は、国家賠償法1条1項の「違法な行為」に該当するのかが問題となった事案です。重要な判旨は以下の部分です。
…。したがって、当該業者の不正な行為により個々取引関係者が損害を被った場合であっても、具体的事情の下において、知事等に監督処分権限が付与された趣旨・目的に照らし、その不行使が著しく不合理と認められるときでない限り、右権限の不行使は、当該取引関係者に対する関係で国家賠償法一条一項の適用上違法の評価を受けるものではないといわなければならない。
上記判旨の赤字下線部分は重要なので、暗記しましょう。結論としては、知事の行為は違法ではありませんでした。
権限不行使の事案の場合は、権限を行使した事案と比較すると、違法と認められる可能性は低い、ということです。
その他、覚えるべき判例3つ
権限不行使に関して覚えるべき判例は以下の3つです。いずれの判例も、リーディングケースの判旨を引用しつつ、事案ごとの個別具体的な事情を総合的に考慮した上で、結論を出しています。
| 事案 | 結論 |
|---|---|
| 医薬品の副作用による被害が発生した場合に、被害の発生のために権限を行使しなかった厚生大臣の違法性(H7.6.23) | 当時の医学的・薬学的知見からして、権限不行使は違法ではない。 |
| 石炭鉱山において、粉塵発生防止策を講じなかった通商産業大臣の違法性(H16.4.27) | 鉱山保安法や当時の事実関係からして、権限不行使は違法。 |
| 水俣病の発生及び被害拡大の防止のために規制権限を行使しなかった国・県の違法性(H16.10.15) | 水質二法や当時の事実関係からして、権限不行使は違法。(国、県共に) |
判旨の細かい暗記は不要ですが、最低限結論だけは押さえましょう。
ポイント②:国家賠償法2条に関する判例を理解しましょう。
出題頻度は低いものの、国家賠償法第2条に関する判例も出題されるので、押さえておきましょう。
第二条
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
特に第2条第1項の前半部分が重要です。管理の客体として例示されているのは、「道路」「河川」「その他の公の営造物」で、該当する行為の類型は「設置又は管理(の)瑕疵」です。
「設置又は管理の瑕疵」
「公の営造物の設置又は管理の瑕疵」とは、「公の営造物が通常有する安全性を欠いていること」をいいます。(判例によって明確に定義されています。)また、当該認定に当たり、過失の存在は必要とされません。
設置または管理の瑕疵に該当するかの判断にあたっては、①当該営造物の構造や②(本来の)用法、③場所的環境、④利用状況などを総合的に考慮し、個別具体的に判断すべき、とするのが判例理論です。4つの判断基準については、可能であれば暗記しておきましょう。
覚えるべき判例・キーワード(7個)
以上でまとめたことを基に、以下覚えるべき判例7つを、客体と結論毎にまとめました。
| 客体(事案) | 結論(要旨一部抜粋) |
|---|---|
| 道路での落石・崩土の発生(S45.8.20) | 管理に瑕疵あり。 (予算措置に困却していた事情は考慮されない。) |
| 道路での故障者の放置(S50.7.25) | 管理に瑕疵あり。 |
| 未改修河川(自然公物)の管理(S59.1.26) | 管理に瑕疵なし。 (過渡的な安全性で足りる。) |
| 改修済河川の管理(H2.12.13) | 管理に瑕疵あり。(※差戻審判決) (予測かつ回避し得る程度の安全性を備えるべき。) |
| 点字ブロック(その他の公の営造物)の設置 (S61.3.25) | ※結論なし。(和解成立のため。) 上記4つの判断基準を具体的に例示した。 |
| 審判台(その他の公の営造物)の設置の瑕疵 | 管理に瑕疵なし。 (本来の用法に従った使用ではない。) |
| 空港(その他の公の営造物)設置使用による損害 (※併用関連瑕疵の事案)(S56.12.16) | 管理に瑕疵あり。 (危害の発生は、営造物の利用者に対してのみならず、 利用者以外の第三者に対するそれも含むものと解すべき。) |
細かい論点は多々ありますが、まずは客体と判旨(赤字マーク部分をメイン)を暗記するよう心がけてみてください。
まとめ:本記事で紹介した21の判例の結論・キーワードを覚えましょう。
はい、国家賠償法について解説してみましたが、いかがでしたでしょうか。
国家賠償法は条文が少ないので、条文の暗記事項は少ないです。判例からの出題が多いため、本記事で21の判例を紹介しました。まずはこれらの判例を覚えてください。(細かい文言の暗記までは不要ですが、結論やキーワードは覚えておきましょう。)
国家賠償法は得点源にしやすいので、判例をきちんと理解して、本番ではぜひ満点を目指しましょう。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければ、他の行政法の「5分で解説シリーズ」もご覧ください。
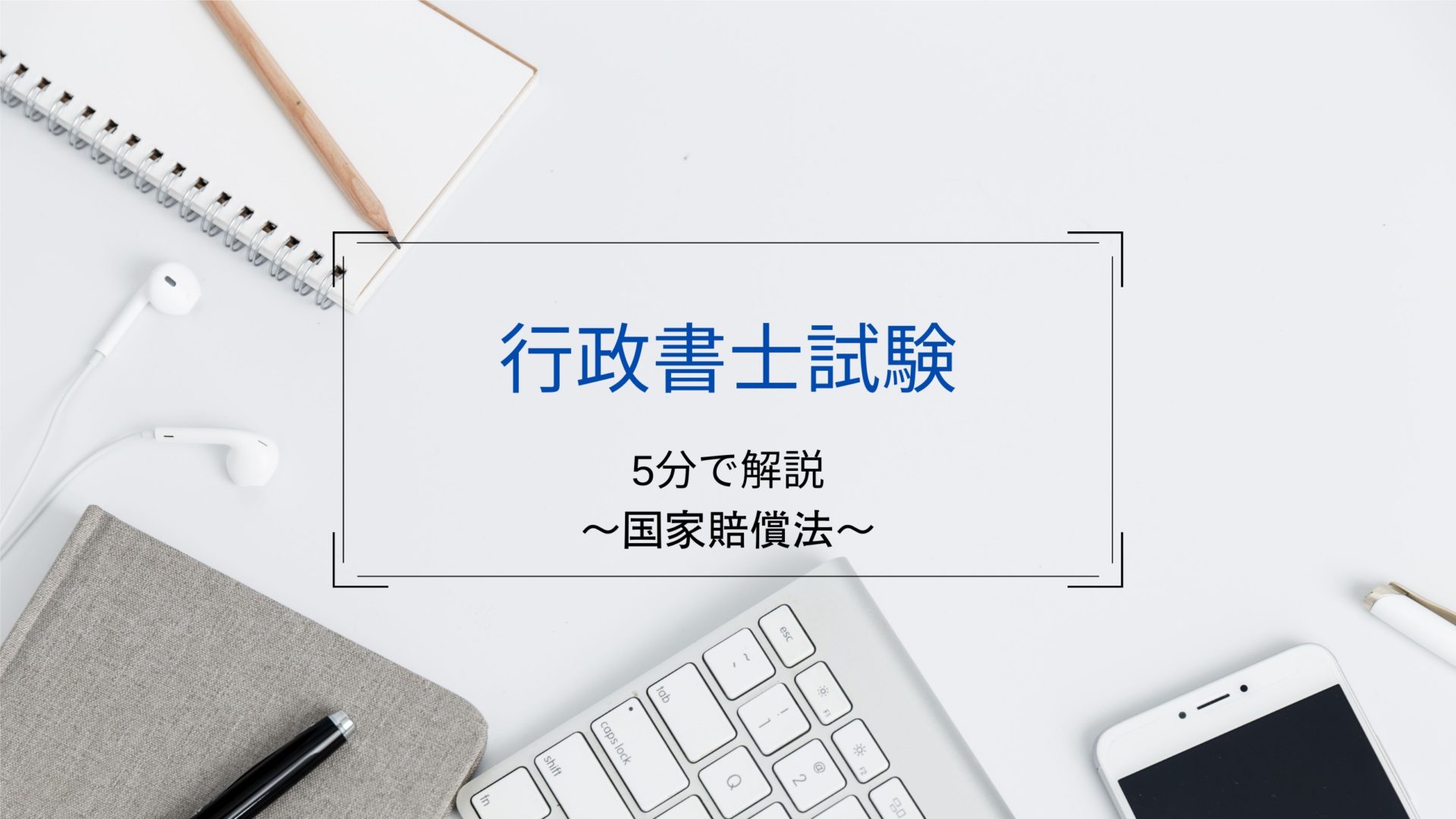
コメント