どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
行政書士試験に限らず、いかなる試験でも過去問対策は重要です。過去問を全く解かないで本番に臨む、というのはあまりにも無謀といえます。
もっとも、過去問対策の具体的な方法について悩んでいる方が多いのではないでしょうか。
私は、2020年の行政書士試験に独学で1発合格することができました。
そんな私が、おすすめの過去問対策について本記事で紹介します。参考になりますと幸いです。
解く量:最低3年分
どの試験にも共通することですが、まずは「敵を知る」ことが大事です。この点、過去問を解くことによって、時間配分・実際の問題の出題のされ方を身に付けることが出来ます。
そのため、最低限過去問は解きましょう。(過去問を全く解かない、というのはさすがに無謀です。)
まず、過去問を解く量ですが、最低3年分を解けばOKです。
やみくもに過去問を解く人がいますが、行政書士試験の場合、過去問を解く量を増やしてもあまり意味がないと考えています。なぜなら、過去問と類似の問題が出題される可能性は低いからです。
あくまでも、出題形式や難易度を確かめる程度に過去問を解けばOKです。
過去問から、出題範囲・出題傾向が予想できる。
行政書士試験の中でも、特に「商法・会社法」や「地方自治法」に関しては、過去問より出題傾向が掴めます。(いずれも試験範囲がそこまで広くない科目です。)
本試験の出題範囲を予想するためにも、過去問を研究しておくことは大事です。問題を丁寧に解くというより、出題範囲を予想する意味合いで過去問を解きましょう。
間違えた問題は、間違えた理由と今後の対策を考える。
過去問を解いて満足するのではなく、間違えた理由についても確認しておきましょう。過去問題集には解説が付属しているので、解説までしっかり確認しておきましょう。
そして、「条文が暗記できていなかった…。」「⚪︎⚪︎の定義が分かっていなかった…。」など、間違えた原因を自分なりに見つけ出しましょう。そして、間違えた原因をもとに、たとえば「もっと条文を読み込む。」など、普段の学習を見直しましょう。
こうすることで、次回からは間違いを減らすことができます。
今後の勉強法を見直すきっかけづくりのため、過去問を解くことが大事になります。
おすすめの過去問題集3冊
私がおすすめする分野別の過去問題集を3冊載せておきます。よろしければ使ってみてください。
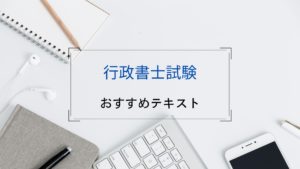
まとめ:過去問はあくまでも傾向や理解度を知るために解きましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。
当然ながら、過去問を解いて内容を理解するだけでは、試験に合格することはできません。
あくまでも出題傾向の把握や理解度の把握のために、過去問を解きましょう。
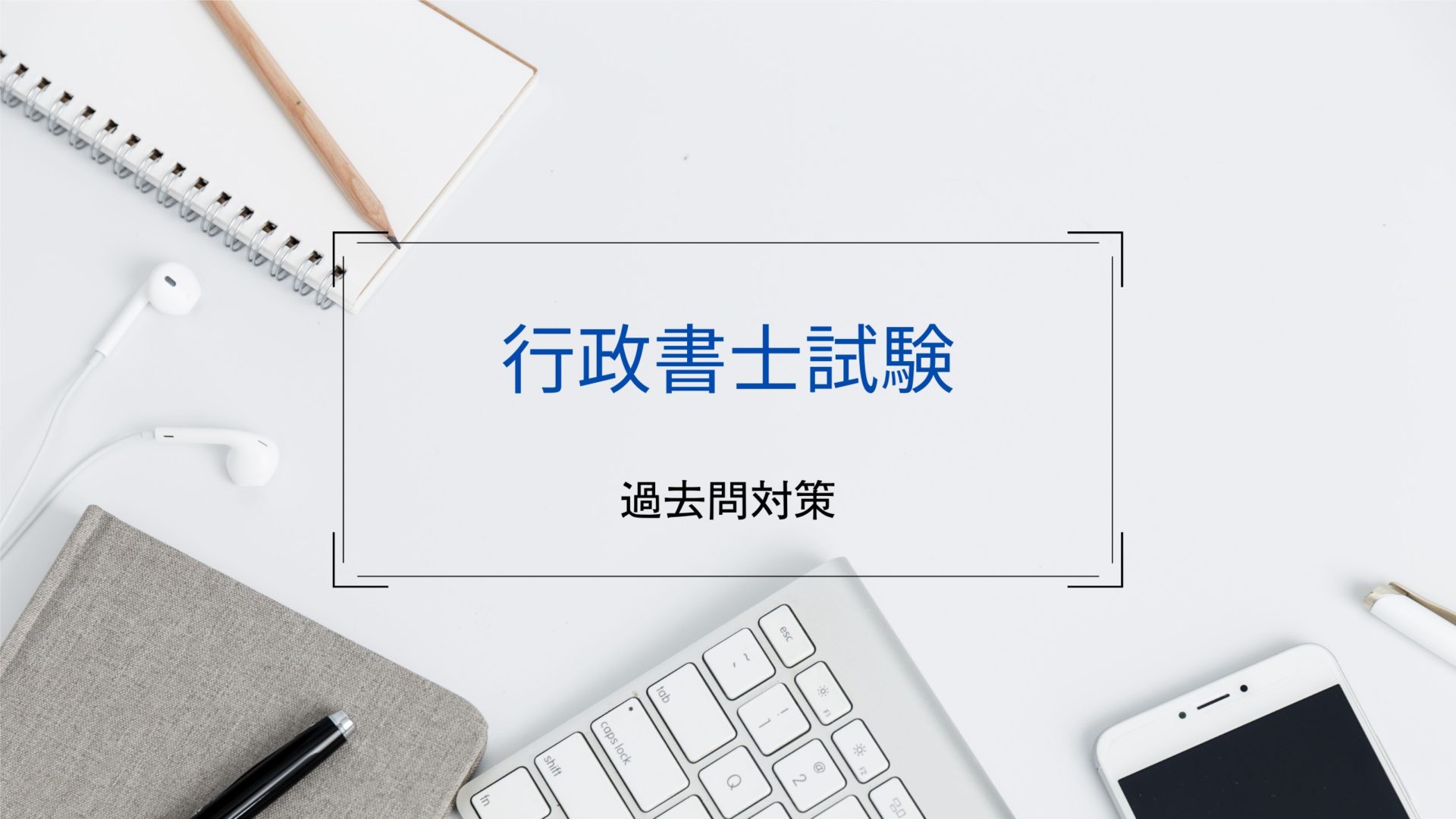



コメント