どうもみなさんこんにちは、Flybirdです。
行政書士試験の法令科目は「法学基礎」「憲法」「行政法」「民法」「商法」の計5科目あります。このうち、後回しになってしまいがちなのが商法です。
商法・会社法からは毎年5問しか出題されないにもかかわらず、試験範囲は広いため、行政法や民法ほど重点的に学習する必要はありませんが、ある程度効率よく勉強することが大事です。とはいっても、初学者の方は、効率の良い商法の学習方法が分からないのではないでしょうか。
私は、2020年の行政書士試験に独学で一発合格することができました。
そんな私が、本記事にて、商法の過去問の出題傾向、出題傾向を踏まえた対策方法を解説します。これから商法の学習を始める方の参考になりますと幸いです。
出題数・配点割合
法令科目の点数内訳と配点割合をまとめたものが以下の表になります。
| 科目 | 5肢選択式 | 配点 | 多肢選択式 | 配点 | 記述式 | 配点 | 合計 | 配点割合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎法学 | 2問 | 8点 | 8点 | 3% | ||||
| 憲法 | 5問 | 20点 | 1問 | 8点 | 28点 | 11% | ||
| 行政法 | 19問 | 76点 | 2問 | 16点 | 1問 | 20点 | 112点 | 46% |
| 民法 | 9問 | 36点 | 2問 | 40点 | 76点 | 31% | ||
| 商法 | 5問 | 20点 | 20点 | 8% | ||||
| 合計 | 40問 | 160点 | 3問 | 24点 | 3問 | 60点 | 244点 | 100% |
行政書士試験は全部で60問出題されますが、このうち商法は計5問(全て5肢選択式)出題されます。
法令科目の合計は244点ですが、そのうちの20点(割合換算すると8%)を商法が占めています。
過去5年分の出題範囲(5肢選択式)
過去5年分の商法の試験範囲を以下の表にまとめました。
| No. | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 問題36 | 商人・商行為 | 商行為の代理 | 運送人の責任 | 商行為 | 営業譲渡 |
| 問題37 | 設立 | 設立 | 設立 | 設立 | 発行可能株式 |
| 問題38 | 譲渡制限株式 | 株主の権利 | 株式の取得 | 株券の質入れ | 株式売渡請求 |
| 問題39 | 社外取締役 | 取締役 | 株主総会 | 社外役員 | 株主の権利 |
| 問題40 | 剰余金の配当 | 機関各論 | 公開会社 | 剰余金の配当 | 会計参与 |
憲法の試験範囲は、「商法」「会社法」の2つの分野に大分できますが、毎年商法が1問、会社法が4問出題されます。なので、まずは出題数の多い「会社法」分野の勉強から始めましょう。
得点目標:人により異なる。(捨ててもOK)
配点割合としては8%と低いため、「対策が必要」という意見と、「捨ててもOK」という意見の両方の意見があります。
どちらの意見も分かりますが、私の個人的意見としては、商法・会社法は捨ててもOKです。
理想を言えば、商法・会社法もきちんと勉強した方が良いのは間違いありません。ただ、勉強時間が限られている中で、商法・会社法分野までしっかり学習できる方は少ないのではないでしょうか。
法令科目の中で重要なのは「民法」・「行政法」・「憲法」の3科目です。まずは、この3つの科目をメインに学習するのが大事です。
憲法・行政法・民法の学習をして、時間に余裕が出来たら商法・会社法分野に取り掛かる、という勉強方針で問題ないです。
なお、私がおすすめする本番の得点目標は、↓の記事で紹介しております。
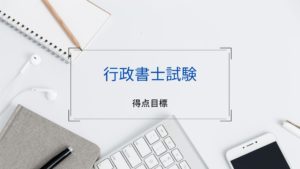
勉強方法:ポイントを絞って学習しよう。
以下、商法・会社法を勉強するとした場合の学習方法を紹介します。
商法・会社法は試験範囲が広いわりに出題数が少ないので、ポイントを絞って学習することが大事です。
以下、商法・会社法の学習方法をそれぞれまとめました。
先に、会社法の勉強方法を説明します。
会社法【問題37~40】について
会社法の試験範囲は、大きく分けると以下の通りです。
- 設立
- 株式
- 新株予約権
- 機関
- 計算等・その他
出題頻度が多く、点が取りやすい分野が「機関」の章です。毎年1〜2問は必ず出題されています。
具体的には「株主総会」「役員(取締役など)」「公開会社と非公開会社の違い」などです。学習に時間が取れない時でも、まずは機関の範囲だけは学習しておきましょう。
また、過去問を見ても、特に、株主総会(議題提出権、招集通知関連)、機関の設置(ex.株式会社は一人または二人以上の取締役を置かなければならない。)は出題可能性が高いです。条文の暗記が必要になるので、根気強く取り組みましょう。
次に出題可能性が高い分野が、「株式」と「設立」の章です。これらの範囲から、毎年1問程度の出題があります。
「株式」は、株式、株式の譲渡、株式の発行等が主な出題範囲です。「設立」は、設立手続、発起人の責任等が主な出題範囲です。ここでも条文の暗記が必要になるので、根気強く取り組みましょう。
その他、「新株予約権」や「計算等」などの出題範囲になっていますが、出題頻度は低く、数年に一度出題される程度です。これらの範囲は深く学習する必要はなく、とりあえず過去問を解いておけばOKです。
商法【問題36】について
商法の試験範囲は、大きく分けると以下の通りです。
- 総則(1条〜31条)
- 商行為・総則、売買、交互計算(501条~534条)
- 商行為その他(533条〜617条)
内容を理解するためには、「商行為・総則、売買、交互計算」→「総則」→「商行為その他」の順番で勉強するのがおすすめです。
わずか1問しか出題されないため、直近の試験の出題範囲を確認し、ある程度ヤマを張って学習してもOKです。
まとめ:思い切って「捨てる」でよい。時間が余れば対策しましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。
商法・会社法にまでなかなか手が回らないと思うので、思い切って捨てても問題ないですが、安心して合格できるようなレベルに達したい人は、商法会社法分野では5問中3問は得点したいところです。
他科目の学習度合いから、商法・会社法をどの程度学習するかどうか決めておきましょう。
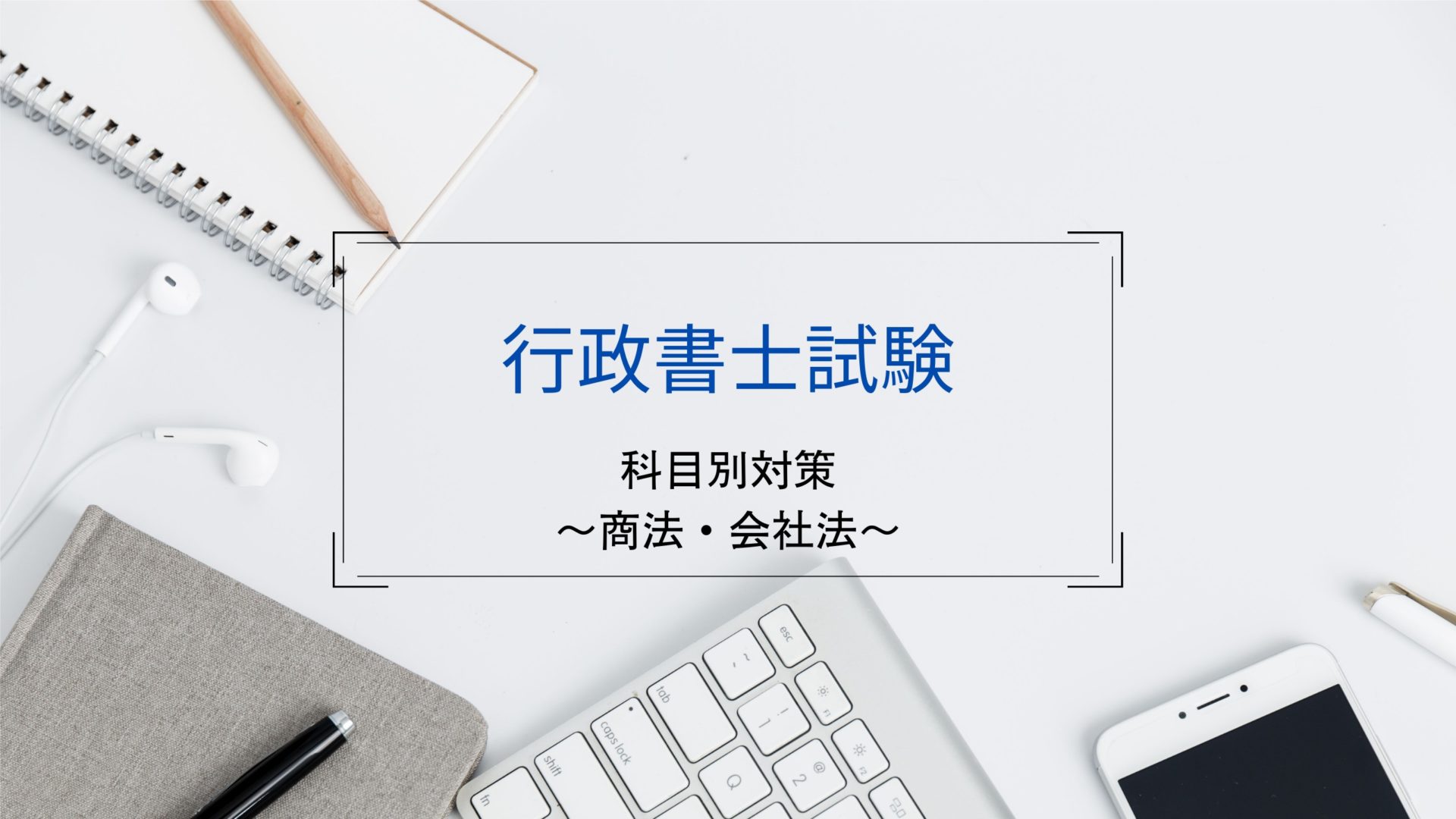
コメント